身近な方が亡くなられた深い悲しみの中、葬儀の準備を進めなければならないご遺族の方、また、故人を偲び参列を考えている方へ。
「何から手をつければいいのかわからない」
「マナーで失敗して、失礼にあたらないだろうか」
「家族葬にしたいけれど、誰をどこまで呼べばいいの?」
突然のことで、多くの方がこのような不安や疑問を抱えています。
この記事では、葬儀の準備から当日の流れ、立場別のマナー、そして近年増加している家族葬の注意点まで、やるべきことの全てを網羅的に解説します。
厚生労働省などの公的データも踏まえ、後悔のない、心のこもったお見送りができるよう、順を追ってご案内します。まずはこの記事で全体像を掴み、落ち着いて準備を進めていきましょう。
葬儀全体の流れと準備スケジュール
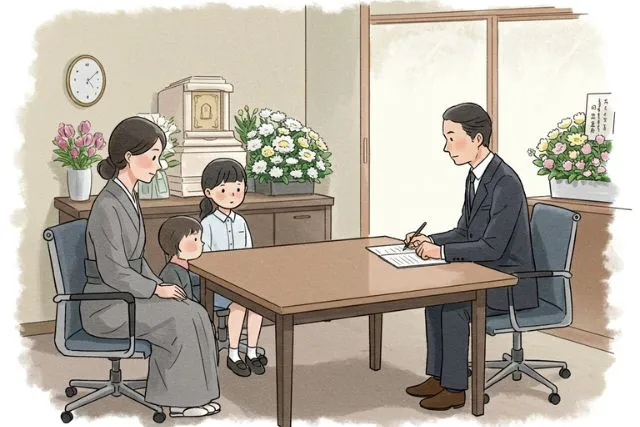
ご逝去から葬儀後までには、決められた期間内に行うべき手続きと儀式が数多くあります。特に都市部では火葬場の予約が混み合っており、日程調整が重要になります。まずは全体像を把握し、冷静に進めましょう。
【ご逝去直後〜3日目頃までの主な流れ】
- ご逝去・ご搬送: 医師から死亡診断書を受け取ります。葬儀社に連絡し、ご遺体を安置先(ご自宅または斎場の安置施設)へ搬送してもらいます。
- 安置・枕飾り: ご遺体を安置し、枕経(まくらぎょう)をあげてもらいます。
- 葬儀の打ち合わせ: 喪主を決定し、葬儀の形式、日程、場所、費用など詳細を葬儀社と打ち合わせます。
- 関係者への連絡: ごく近しい親族を中心に訃報を伝えます。
- お通夜: 一般的にご逝去の翌日の夜に行われます。僧侶の読経、焼香、通夜振る舞いなどが行われます。
- 葬儀・告別式: お通夜の翌日に行われることが多く、故人との最後のお別れの儀式です。
- 出棺・火葬・収骨: 告別式後、火葬場へ移動し、火葬、収骨(お骨上げ)を行います。
【葬儀後の主な儀式】
- 初七日法要: 本来は亡くなった日から7日目に行いますが、近年では火葬と同日に行う「繰り上げ初七日」が主流です。
- 四十九日法要・納骨: 忌明けとされる大切な法要です。この日に合わせて納骨を行うことが多くなります。
死亡届の提出(7日以内)や火葬許可証の申請といった役所手続きは、通常、葬儀社が代行してくれます。まずは信頼できる葬儀社へ連絡することが、その後の流れをスムーズに進める第一歩です。
▶︎ さらに詳しく: 葬儀の時間は午後からでもOK?開始時間の決め方
弔いと供養の基本的な考え方

「弔い(とむらい)」と「供養(くよう)」は似ていますが、少し意味合いが異なります。
- 弔い: 故人の死を悼み、悲しむ気持ちを表す行為全般を指します。お通夜や葬儀・告別式は、社会的に故人の死を悼むための代表的な儀式です。
- 供養: 故人の冥福を祈り、追善(ついぜん)の行いをすることです。読経や焼香、お墓参りなどを通じて、故人が安らかであるように祈ります。
葬儀は「弔い」の儀式であると同時に、故人の冥福を祈る「供養」の始まりでもあります。宗派による違いはありますが、故人を想う気持ちが最も大切であることに変わりはありません。
▶︎ さらに詳しく: 弔いと供養の違いとは?意味と目的を解説!
【立場別】必ず押さえるべき葬儀の基本マナー

葬儀の場では、遺族側も参列者側も、故人への敬意と他の参列者への配慮が求められます。ここでは最低限押さえておきたい基本マナーを解説します。
言葉遣い・忌み言葉
お悔やみの言葉を伝える際は、不幸が重なることを連想させる「重ね言葉」(例:たびたび、くれぐれも)や、直接的な「死」「生きる」といった表現は避けるのがマナーです。これらを「忌み言葉(いみことば)」と呼びます。
- お悔やみの言葉(例): 「このたびはご愁傷様です」「心よりお悔やみ申し上げます」
- 避けるべき言葉(例):
- 重ね言葉:重ね重ね、たびたび、またまた
- 不幸が続くことを連想させる言葉:追って、続いて
- 直接的な表現:死亡、ご存命中
「お葬式」と「ご葬儀」、どちらを使うべきか迷うこともありますが、「ご葬儀」がより丁寧な表現です。
▶︎ さらに詳しく: ご葬儀の正しい言い方と心得るべきマナーとは?
香典・挨拶・お礼の対応
香典は、故人への供養の気持ちを表すものです。遺族にとっては、葬儀費用の一部を支えるという相互扶助の意味合いもあります。
- 遺族側: 受付の準備、香典の管理、そして香典返し(即日返し or 後返し)の手配が必要です。喪主は、通夜や告別式の最後に参列者へ挨拶を行います。
- 参列者側: 新札は避け、旧札を香典袋に入れます。表書きは宗教・宗派に合わせ(例:御霊前、御仏前)、自身の名前をフルネームで記入します。受付で渡す際は、「このたびはご愁傷様です」など一言添えるのが丁寧です。
やむを得ない事情で香典だけを渡してすぐに帰る場合や、遺族からお礼を言われた際の返し方にも、相手を気遣うマナーが存在します。
▶︎ さらに詳しく:
【形式別】一般葬と家族葬の違いと進め方
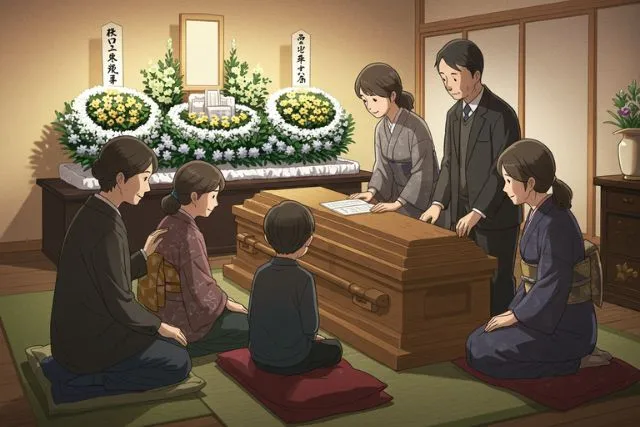
近年、葬儀の形式は多様化しており、特に「家族葬」を選ぶ家庭が増えています。
- 一般葬: 親族、友人、会社の同僚、近所の方など、故人と生前に関わりのあった方を広く招いて行う伝統的な形式の葬儀です。
- メリット:多くの方に故人を見送ってもらえる、社会的な義理を果たせる。
- デメリット:費用が高額になりがち、参列者への対応で遺族の負担が大きい。
- 家族葬: 参列者を家族やごく親しい親族・友人に限定して行う、小規模な葬儀です。
- メリット:故人とゆっくりお別れができる、費用を抑えられる、遺族の精神的・身体的負担が少ない。
- デメリット:後から訃報を知った方が自宅へ弔問に来られ、その対応が必要になることがある。誰を呼ぶかの線引きが難しい。
どちらの形式を選ぶかは、故人の遺志や遺族の考え方、人間関係によって決まります。特に家族葬は、参列をお断りする方への配慮が非常に重要になります。
家族葬で直面しがちな人間関係Q&A
家族葬はプライベートな儀式である一方、親族間のデリケートな問題に発展しやすい側面もあります。「誰を呼ぶか」「香典はどうするか」など、事前に家族内でよく話し合っておくことがトラブル回避の鍵です。
ここでは、よくある具体的なお悩みと、それに対応する詳しい解説記事をご紹介します。
【親族・親戚との関係】
- 実の親の葬儀に嫁いだ娘は香典を包む?家族葬のマナーを解説
- 嫁いだ娘が親の葬儀で香典を包む時の名前の書き方と注意点
- 親の葬儀に参列する嫁いだ娘の服装と心得とは?
- 義父の葬儀に参列する嫁の服装選び【喪主・身内別】
- 家族葬に義両親は呼ぶべき?参列の断り方と注意点
- 家族葬に義理の兄弟は呼ぶべき?参列マナーと香典相場
- 孫の嫁は家族葬に参列すべき?事前準備と注意点
- 家族葬に孫は参列すべき?呼ばない場合のマナーと配慮
【運営・会社対応】
【葬儀後のフォロー】
費用トラブルを防ぐための葬儀社の選び方
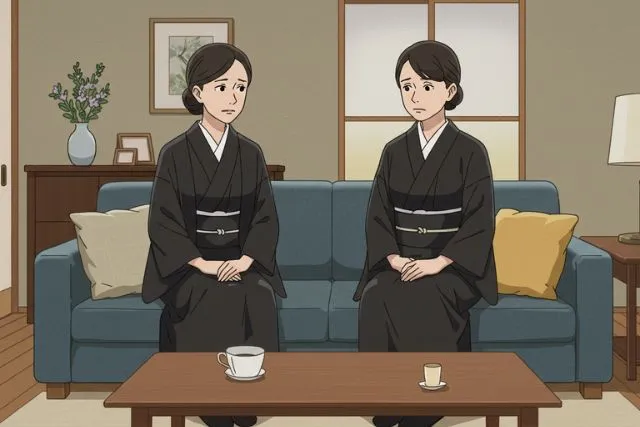
葬儀にはまとまった費用がかかります。そして残念ながら、「見積もりにない追加請求をされた」といった費用に関するトラブルは、国民生活センターにも数多く寄せられています。
後悔しない葬儀を行うためには、信頼できる葬儀社を選ぶことが何よりも重要です。
【葬儀社選びの3つのポイント】
- 見積もりの明瞭さ: 見積書に「一式」という表記が多くないか、含まれるもの・含まれないものが具体的に記載されているかを確認しましょう。特に「飲食費」「返礼品費」「宗教者へのお礼」は別途必要になることが多い項目です。
- 丁寧な対応: こちらの質問に真摯に答えてくれるか、故人や遺族の気持ちに寄り添った提案をしてくれるか、スタッフの対応をよく見極めましょう。
- 複数社の比較検討: 可能であれば、2〜3社から見積もり(相見積もり)を取り、内容と費用を比較検討することをお勧めします。焦って1社に決めてしまうと、後から後悔する可能性があります。
最近では、インターネットで複数の葬儀社のプランを比較し、一括で見積もりを依頼できるサービスもあります。こうしたサービスを活用することで、手間をかけずに、地域の優良な葬儀社を見つけることができます。
まとめ:故人を偲び、心穏やかに見送るために
葬儀は、故人との最後のお別れの場であると同時に、遺された人々が悲しみを乗り越え、新たな一歩を踏み出すための大切な儀式でもあります。
突然のことで戸惑うことも多いかと思いますが、やるべきことを一つひとつ整理していけば、必ず心のこもったお見送りができます。
この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、後悔のない葬儀を行うための一助となれば幸いです。もし具体的なマナーや手順で迷った際には、各章でご紹介した詳細記事もぜひご参照ください。
