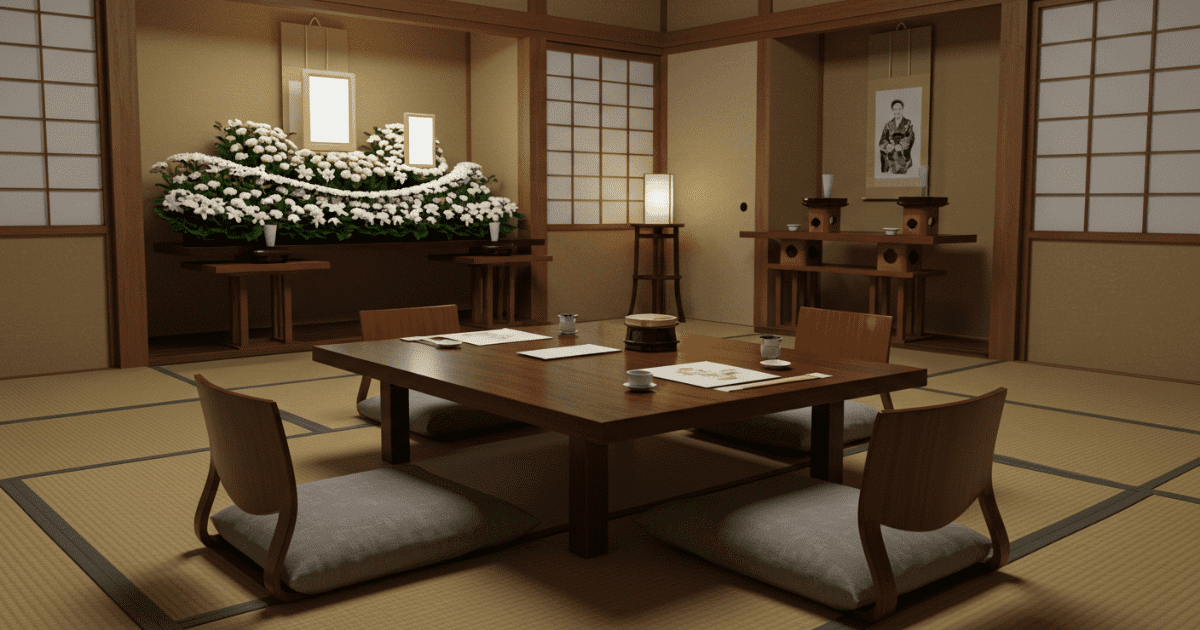「法要を午後に行う予定だけど、御膳料はどうすればいいの?」「会食なしの場合、御膳料はいくら包めば失礼がない?」「そもそも、午後の法要で御膳料は必要なの?」
このようにお悩みではありませんか?
法要、特に午後の法要となると、御膳料の相場やマナーについて、わからないことが多いですよね。インターネットで「法要 午後 御膳料」と検索しても、情報が断片的だったり、古い情報だったりして、結局どうすれば良いのか迷ってしまうこともあるでしょう。
この記事では、そんな法要 午後 御膳料に関する疑問を全て解決します!
- 午後の法要での御膳料の相場が明確になる
- 会食なしの場合の、お寺や親族への適切な御膳料の金額がわかる
- 御膳料の正しい渡し方、封筒の書き方など、具体的なマナーが身につく
- 午後からの法事を行う際の注意点や、食事の扱いについて理解できる
法要午後の御膳料相場とマナー

【法事】御膳料はいつ渡す?(会食なしの場合)
法事の後、会食を設けない場合、御膳料を包むことがあります。この御膳料、一体いつ渡せば良いのか、タイミングに迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。「早すぎても失礼にあたる?」「後から渡すのはダメ?」など、様々な疑問が浮かびますよね。結論から言うと、御膳料を渡すタイミングは、法要の当日、法要が始まる前か終わった後が一般的です。
タイミングに迷ったら、お寺の方に事前に確認するのが一番確実です。『御膳料はいつお渡しすればよろしいでしょうか?』と聞けば、丁寧な印象にもなりますよ。
その理由は、法要前であれば、お寺の方が御膳料を事前に確認でき、準備がしやすくなるからです。法要後であれば、お礼の言葉とともに、感謝の気持ちを直接伝えることができます。「本日はありがとうございました」と一言添えて渡すと、より丁寧な印象になりますね。
具体的な例としては、法要が始まる前に受付で渡すか、法要後にお寺の方に挨拶をする際に渡すのが良いでしょう。法要の規模が大きい場合は、受付に「御膳料」と書かれた箱が用意されていることもあります。ただし、お寺によっては、渡すタイミングを指定される場合もありますので、事前に確認しておくと安心です。「御膳料はいつお渡しすればよろしいでしょうか?」と伺いを立ててみましょう。
【ちょっとした注意点】
御膳料を渡す際、お札の向きにも気を配りましょう。封筒の表側にお札の肖像画が来るように入れ、肖像画が上になるように渡すのがマナーです。細かいことですが、こういった心遣いが、故人を偲ぶ気持ちを表すことにつながります。
御膳料3000円はマナーとして失礼?
3,000円という金額について、気になる方が多いようですね。実際のところ、適切かどうかは状況次第です。
「御膳料3000円」というキーワードで検索される方が多いようです。3,000円という金額は、果たして失礼にあたるのでしょうか?結論として、3,000円の御膳料は、状況によっては失礼にあたる可能性があります。
主な理由としては、一般的な会食の費用相場よりも低い金額であるためです。前述の通り、法事後の会食は、1人あたり5,000円~20,000円程度が相場です。3,000円では、この相場を大きく下回ってしまい、「故人を偲ぶ気持ちが足りない」と受け取られてしまう可能性があります。
具体的な例として、法事の後に簡単な軽食(お弁当など)を用意する場合を考えてみましょう。お弁当代が1人3,000円程度であれば、御膳料として3,000円を包むのは妥当かもしれません。しかし、会食を全く行わない場合は、3,000円では少ないと感じられる可能性があります。特に、故人と親しい間柄だった場合は、もう少し金額を上乗せすることを検討しましょう。
ただし、これも地域や状況によって異なります。「御膳料」ではなく、「御車代」や「寸志」として3,000円を包む場合は、失礼にあたらないこともあります。寸志とは、文字通り「わずかな気持ち」を表すものですので、金額が少なくても問題ありません。「御車代」は、遠方から来ていただいた方への交通費としてお渡しするものです。不安な場合は、年長者や親戚に相談してみるのが良いでしょう。
【こんな場合はどうする?】
もし、経済的な事情でどうしても3,000円しか包めない場合は、無理をする必要はありません。大切なのは、金額よりも故人を偲ぶ気持ちです。手紙を添えたり、お花を供えたりするなど、別の形で感謝の気持ちを表すこともできます。
親戚への法事御膳料(会食なし)の相場
親戚への法事の御膳料(会食なし)の相場は、故人との関係性や地域の慣習によって異なりますが、一般的には5,000円~10,000円程度が目安となります。
金額に幅があるのは、故人との関係性が近いほど、また、地域の慣習として高額を包む傾向があるほど、金額が高くなる傾向にあるからです。例えば、故人が自分の親である場合と、遠い親戚である場合では、包む金額が異なるのは自然なことです。「親しき仲にも礼儀あり」という言葉があるように、親しい間柄であっても、適切な金額を包むようにしましょう。
具体的な例を挙げると、故人が自分の親で、一周忌の法要を行う場合、1人10,000円を包むことが多いでしょう。一方、故人が叔父や叔母で、三回忌の法要であれば、5,000円程度を包むのが一般的です。ただし、これはあくまでも目安です。地域によっては、独自の慣習がある場合もありますので、注意が必要です。
金額を決める際は、他の親族と相談し、足並みを揃えることが大切です。
親戚同士で包む金額に差があると、失礼に思われることはありませんか?
基本的には問題ありませんが、特に近しい親戚同士では、事前に相談して金額を揃えておくと安心です。『皆さんどのくらい包む予定ですか?』と軽く聞いてみるとよいでしょう。
特に、年長者の意見を参考にすると良いでしょう。また、地域の慣習に詳しい年長者に相談するのも良いでしょう。「この地域の相場はどのくらいですか?」と率直に尋ねてみるのも一つの方法です。
【相場表】
| 故人との関係性 | 法要の種類 | 御膳料の相場 |
|---|---|---|
| 親 | 一周忌 | 10,000円~ |
| 兄弟・姉妹 | 一周忌 | 5,000円~ |
| 叔父・叔母 | 三回忌 | 5,000円~ |
| その他の親戚 | 三回忌 | 3,000円~ |
お寺での法事の御膳料相場と渡し方
お寺での法事の場合、御膳料の相場は、5,000円~20,000円程度が一般的です。ただし、お寺との関係性や法要の規模によっても金額は異なります。檀家総代など、お寺との関係が深い場合は、より高額を包むこともあります。
この金額になる理由は、お寺への御膳料には、食事代だけでなく、お布施の意味合いも含まれているからです。お布施とは、お寺への感謝の気持ちを表すものであり、読経や法話などのお勤めに対するお礼としてお渡しします。お布施は、法要の規模や内容に応じて金額を調整します。
具体的な渡し方としては、白い封筒(不祝儀袋)に「御膳料」と表書きし、お布施とは別に渡すのがマナーです。
不祝儀袋とは、弔事の際に金銭を包むための封筒です。
表書きとは、不祝儀袋の表面に書く、贈り物の名目(例:御膳料、御布施)のことです。
渡すタイミングは、法要の前、または法要後にお寺の方にお礼を述べる際が良いでしょう。「本日はよろしくお願いいたします」と一言添えて渡すと、より丁寧な印象になります。
注意点として、お寺によっては、御膳料を受け取らない場合もあります。事前に確認しておくか、もし受け取ってもらえなかった場合は、お布施に上乗せして渡すようにしましょう。その際は、「御膳料としてお渡ししようと思いましたが、お受け取りいただけないとのことでしたので、お布施としてお納めください」と一言添えると良いでしょう。
百箇日法要での御膳料の金額相場
百箇日法要での御膳料の金額相場は、他の法要と同様に、5,000円~20,000円程度が一般的です。
百箇日法要は、故人の死後100日目に行われる重要な法要であり、他の法要と比べて特別な意味合いを持ちます。そのため、御膳料の金額も、他の法要と同等、またはそれ以上にすることが多いです。しかし、必ずしも高額でなければならないというわけではありません。故人を偲ぶ気持ちが大切です。
具体的な金額は、故人との関係性や地域の慣習によって異なります。例えば、故人が自分の親である場合は、10,000円~20,000円を包むことが多いでしょう。一方、故人が親戚である場合は、5,000円~10,000円程度が目安となります。
百箇日法要は、四十九日法要と並んで、特に重要な法要とされています。この時期は、故人の魂が完全に仏様の世界へ旅立つと考えられているため、遺族にとっても区切りの法要となります。故人を偲び、感謝の気持ちを込めて、適切な金額を包むようにしましょう。また、百箇日法要は、卒哭忌(そっこくき)とも呼ばれ、「泣くことをやめる日」という意味があります。悲しみを乗り越え、新たな一歩を踏み出すための節目とも言えるでしょう。
法要午後の御膳料の渡し方注意点

法事(会食なし)御膳料はいつ渡す?
法事(会食なし)の場合、御膳料をいつ渡すか迷う方もいるかもしれません。結論から言うと、御膳料を渡すタイミングは、法要の当日、法要が始まる前か終わった後が一般的です。
法要前に渡す場合は、お寺の方が事前に御膳料を確認でき、準備がしやすくなります。また、法要後であれば、お礼の言葉とともに、感謝の気持ちを直接伝えることができます。「本日はありがとうございました」と一言添えて渡すと、より丁寧な印象になりますね。
具体的な例としては、法要が始まる前に受付で渡すか、法要後にお寺の方に挨拶をする際に渡すのが良いでしょう。ただし、お寺によっては、渡すタイミングを指定される場合もありますので、事前に確認しておくと安心です。「御膳料はいつお渡しすればよろしいでしょうか?」と伺いを立ててみましょう。
【こんな時はどうする?】
もし、法要に遅刻してしまった場合は、後からお寺の方に直接お渡しするか、後日改めてお渡しするようにしましょう。その際は、「遅れてしまい申し訳ございません」と一言お詫びを添えるのを忘れずに。
御膳料の封筒:選び方と書き方
御膳料を包む封筒は、白い無地の封筒(不祝儀袋)を使用するのが一般的です。水引は、黒白または双銀の結び切りを選びます。結び切りは、「繰り返さない」という意味が込められており、弔事に用いられます。
表書きは、「御膳料」と書きます。「御布施」と間違えないように注意しましょう。御布施は、お寺へのお礼として渡すもので、御膳料とは神職や僧侶が儀式や法要を行った際に、謝礼として渡す金銭のことです。薄墨ではなく、濃い墨で書くのがマナーです。薄墨は、悲しみを表すために用いられますが、御膳料は感謝の気持ちを表すものですので、濃い墨で書きましょう。名前は、表書きの下にフルネームで記載します。
裏面には、住所と金額を記載します。金額は、旧字体で書くのが正式なマナーです。
旧字体とは、「壱、弐、参、伍、拾、阡、萬」などの漢数字のことです。
(例:金伍阡円、金壱萬円)
封筒の選び方や書き方には、地域や宗派によって異なる場合があります。不安な場合は、年長者や葬儀社の方に相談してみるのが良いでしょう。
法事(会食なし)御膳料書き方の注意点
法事(会食なし)の御膳料の書き方で特に注意すべき点は、「御膳料」と明確に記載することです。「御布施」と混同しないように注意が必要です。
「御膳料」と明記する必要があるのは、お寺側が、お布施と御膳料を区別しやすくするためです。御膳料は、食事の代わりにお渡しするものですので、お布施とは別に用意するのがマナーです。
具体的には、封筒の表書きに「御膳料」と書き、その下に自分の名前をフルネームで記載します。裏面には、住所と金額を旧字体で記載します。
また、薄墨ではなく、濃い墨で書くことも重要なポイントです。薄墨は弔事全般に使うものですが、御膳料は濃い墨で書くのが一般的です。これは、「故人を偲ぶ気持ち」と「感謝の気持ち」をしっかりと表すためです。
【間違えやすいポイント】
「御膳料」と「御食事料」は、どちらも同じ意味で使われます。どちらを使っても間違いではありませんが、「御膳料」の方がより一般的です。
御膳料が必要かどうかの判断基準
御膳料が必要かどうかは、法要後に会食を行うかどうかが基本的な判断基準となります。会食を行わない場合は、御膳料を包むのが一般的です。
会食を行う場合、食事の用意や会場の準備など、お寺や参列者に手間をかけることになります。会食を行わない場合は、その手間を省く代わりに、御膳料として食事代をお渡しする、という考え方です。
ただし、例外もあります。例えば、ごく内輪の法要で、お弁当などを持参する場合は、御膳料は不要となることもあります。また、お寺によっては、御膳料を受け取らない場合もあります。
判断に迷う場合は、お寺や親族に相談してみるのが確実です。
お寺の方から『御膳料は不要』と言われた場合、何か別の形で感謝の気持ちを伝えるべきでしょうか?
その場合は、お布施に気持ちを上乗せしたり、ちょっとしたお供え物を用意するのも良いですね。例えば、お菓子やお花をお渡しすると、心遣いが伝わりやすいですよ。
「今回は会食をしないのですが、御膳料はお渡しした方がよろしいでしょうか?」と率直に尋ねてみましょう。
【こんな場合はどう判断する?】
- 故人の遺志で会食をしない場合: 御膳料を包むのが一般的です。
- 家族だけで簡単な食事をする場合: 御膳料は不要ですが、気持ちとして「御供」などを包むこともあります。
- お寺から「御膳料は不要」と言われた場合: お寺の指示に従いましょう。
午後からの法事は可能?注意点とは
結論から言うと、午後からの法事も可能です。ただし、いくつかの注意点があります。
まず、お寺の都合を確認することが重要です。
午後の法事は可能ですが、お寺の都合や参列者の負担も考慮して、事前にしっかり準備しておくことが大切ですね。
お寺によっては、午後の法要を受け付けていない場合や、時間が限られている場合があります。事前に必ず確認しましょう。「午後に法要をお願いしたいのですが、可能でしょうか?」と、電話やメールで問い合わせてみましょう。
次に、参列者の都合も考慮する必要があります。遠方から来る方がいる場合は、移動時間や宿泊の手配なども考慮し、無理のないスケジュールを組むようにしましょう。特に、高齢の方や小さなお子様連れの方がいる場合は、負担が少なくなるように配慮が必要です。
最後に、食事の準備です。午後からの法事の場合、会食をどうするか、御膳料をどうするかなど、事前に決めておく必要があります。会食を行う場合は、夕食の時間帯になることが多いので、それに合わせた準備が必要です。会食を行わない場合は、御膳料の準備を忘れずに行いましょう。
午後からの法事、食事はどうする?
午後からの法事の場合、食事の扱いは、大きく分けて2つのパターンがあります。
- 会食を行う場合:
- 法要後、夕食の時間帯に会食を行う。
- 通常の法事と同様に、会食の手配が必要。
- 御膳料は不要。
- 会場の手配、料理の注文、飲み物の準備など、事前にしっかりと準備をしておきましょう。
- アレルギーを持つ参列者がいる場合は、事前に確認し、対応できる料理を用意しましょう。
- 会食を行わない場合:
- 法要後、会食は行わず、御膳料を包む。
- 御膳料の相場は、前述の通り、5,000円~20,000円程度。
- お弁当などを用意する場合は、別途、その費用を考慮する。
- お弁当を用意する場合は、参列者の人数分+予備をいくつか用意しておくと安心です。
- 持ち帰り用の袋も用意しておくと、親切ですね。
どちらのパターンを選ぶかは、参列者の人数や、故人との関係性、予算などを考慮して決めましょう。「今回は、故人の希望で会食は行わず、御膳料を包むことにしました」など、参列者の方々へ事前に伝えておくと、よりスムーズです。
法要の御膳料Q&Aよくある質問
Q: 御膳料は、お札をそのまま入れても良いですか?
A: いいえ、御膳料は必ず封筒に入れて渡しましょう。白い無地の封筒(不祝儀袋)を使用し、表書きは「御膳料」と書きます。直接お札を渡すのは、マナー違反となりますので、注意しましょう。
Q: 御膳料は、新札と旧札、どちらが良いですか?
A: 御膳料は、新札でも旧札でも、どちらでも構いません。ただし、あまりにも汚れたお札や破れたお札は避けるようにしましょう。新札の場合は、一度折り目をつけてから入れると、より丁寧な印象になります。
Q: 御膳料を渡す際、お布施と一緒に渡しても良いですか?
A: いいえ、御膳料とお布施は、別々の封筒に入れて渡すのがマナーです。お布施は、お寺へのお礼として渡すものであり、御膳料は食事の代わりにお渡しするものです。それぞれ আলাদাな意味合いを持つため、一緒に渡すのは避けましょう。
Q: 御膳料の金額は、どのように決めたら良いですか?
A: 御膳料の金額は、故人との関係性、地域の慣習、法要の規模などを考慮して決めます。迷う場合は、親族や菩提寺に相談してみましょう。「今回の法要では、御膳料はどのくらい包めばよろしいでしょうか?」と具体的に質問すると、より適切なアドバイスが得られます。
Q: 会食の代わりに、お菓子などを配っても良いですか?
A: 会食の代わりに、お菓子や果物などを配ることもあります。その場合は、「御供」としてお渡しするのが一般的です。「御供」は、故人へのお供え物という意味合いがあります。
Q: 遠方から来てくれた親戚に、御膳料とは別に「御車代」を渡すべきですか?
A: はい、遠方から来ていただいた方には、御膳料とは別に「御車代」を渡すのが一般的です。「御車代」は、交通費の実費、またはそれに近い金額を包みます。
Q: 御膳料を受け取ってもらえなかった場合は、どうすれば良いですか?
A: お寺によっては、御膳料を受け取らない場合があります。その場合は、お布施に上乗せして渡すか、後日改めてお礼の品を持参すると良いでしょう。
法要の御膳料についてのまとめ

法要における御膳料は、会食をしない場合に、食事の代わりとしてお渡しするものです。金額の相場や渡し方には、さまざまなマナーがあります。
この記事では、法要の御膳料について、金額の相場、渡し方、書き方、午後からの法事の場合の注意点など、詳しく解説しました。
御膳料は、故人を偲び、感謝の気持ちを表すための大切なものです。金額だけでなく、渡し方やマナーにも気を配り、故人を供養しましょう。この記事が、皆様の法要準備の一助となれば幸いです。何かご不明な点があれば、いつでもお寺や葬儀社、年長者の方にご相談ください。
まとめ
- 法要で会食がない場合、御膳料は5,000円~20,000円が相場
- 御膳料3,000円は、状況によっては失礼にあたる可能性がある
- 親戚への御膳料は故人との関係性で金額が変わる
- お寺への御膳料には、お布施の意味合いも含まれる
- 百箇日法要の御膳料も、他の法要と相場は変わらない
- 御膳料は法要当日、開始前か終了後に渡すのが基本
- 御膳料は白い封筒(不祝儀袋)に入れ、「御膳料」と表書きする
- 御膳料の書き方は、濃い墨で書き、金額は旧字体で記載する
- 御膳料が必要か否かは、基本的に会食の有無で判断する
- 午後からの法事は可能だが、お寺や参列者への事前確認が必要
- 午後からの法事の食事は、会食か御膳料のどちらかを選択
- 御膳料とお布施は、別々の封筒で渡すのがマナー