定年が近づくと、ふと将来のお金のことが心配になりますよね。
この記事では、老後月20万で一人暮らしという暮らしを実現するために、今からできる具体的な準備と心構えについて、専門家の視点から優しくお伝えします。
【はじめに結論】
| 結論 | 計画的な準備と固定費の見直しで実現可能です。 |
|---|---|
| 鍵となる要素 | 住居費の管理と、今の自分に合った保険への見直しが重要になります。 |
| まずやるべき事 | 現在の家計を正確に把握し、具体的なシミュレーションから始めましょう。 |
この記事で分かること
- 月20万円生活のリアルな家計簿シミュレーション
- 定年前に始めたい具体的な家計の見直し術
- 持ち家と賃貸、それぞれの将来かかる費用
- 将来の病気や介護に備えるお金の知識
- 漠然としたお金の不安を解消するためのヒント
老後月20万で一人暮らしは可能?データで見るリアルな現実

「この先、月20万円でやっていけるかしら…」ふとした瞬間に、そんな思いが頭をよぎることはありませんか?年金のニュースやご友人との会話で、漠然とした不安を感じてしまうのは、あなただけではありません。とても自然なことですよ。
でも、ご安心ください。データに基づけば、その目標は決して手の届かない夢物語ではないのです。大切なのは、正しい知識を持って、今からご自身のペースで準備を始めること。ただそれだけです。
この記事であなたの不安が希望に変わる3つの理由
この記事は、単に一般的な数字をお見せするだけではありません。あなたの不安な気持ちにそっと寄り添い、具体的な行動へと繋げるための「道しるべ」となることを目指しています。
- 理由1:あなたの状況に近いモデルで解説
50代・一人暮らしという視点から、リアルな生活を思い浮かべながら解説します。 - 理由2:専門用語を使いません
難しい金融の話は抜きにして、今日からすぐに実践できる具体的なステップに絞りました。 - 理由3:安心できる未来を描くお手伝い
いたずらに不安を煽るのではなく、「これなら私にもできるかも」と思っていただけるような選択肢を提示します。
計画的な準備があれば月20万円の生活は実現可能です
公的なデータに目を向けてみると、実は老後一人暮らしの平均的な生活費は、月20万円を下回っているのが現状です。
総務省の調査によれば、65歳以上の単身無職世帯の平均的な消費支出は月額14万円台。もちろん、これはあくまで平均値で、お住まいの地域やどんな暮らしをしたいかによって大きく変わります。それでも、月20万円という目標は、平均よりも少しゆとりのある生活を目指せる、十分に目指せる現実的な目標なんです。
| 項目 | 65歳以上単身世帯の平均 | あなたの目標 |
|---|---|---|
| 消費支出(月額) | 約143,139円 | 200,000円 |
| 差額 | - | +56,861円 |
※出典:総務省統計局「家計調査報告(家計収支編)2022年(令和4年)」
このプラスの差額をどう活かすか、あるいは万が一の出費にどう備えるか。それが、心豊かなセカンドライフを送るための鍵となります。
まずはご自身の家計状況を把握することから始めましょう
具体的な計画を立てるための大切な第一歩は、ご自身の「現在地」を知ることです。難しく考える必要はありませんよ。まずは以下のものをテーブルの上に並べて、現状を整理してみませんか?
- ねんきん定期便:将来受け取れる年金額の目安が書かれています。
- 保険証券:現在加入している保険の内容と、月々の保険料を確認できます。
- 預貯金の残高が分かるもの:おおよその貯蓄額を把握しておきましょう。
- 毎月の支出:家計簿がなくても大丈夫。クレジットカードの明細や銀行口座の履歴から、大まかな支出が見えてきます。
これらをただ眺めてみるだけでも、これまで漠然としていたお金の流れが、少しずつ身近に感じられるようになるはずです。
なぜ漠然とした不安が消えない?50代のリアルな悩み

数字の上では可能だと分かっていても、心の中のモヤモヤは、そう簡単には晴れないものですよね。特に定年という大きな節目を前にすると、これまで少し遠い未来のことだと思っていた問題が、急に目の前に迫ってくるように感じられます。その不安の正体を、一つひとつ一緒に解きほぐしていきましょう。
「年金だけでは足りないかも」という漠然とした恐怖心
少し前に世間を騒がせた「老後2000万円問題」のように、世の中には老後のお金に関する少し心配になるような情報が溢れています。「私は本当に大丈夫かしら…」と、年金だけで生活していくことに不安を感じるのは、当然のことです。
特に、長く会社で勤めてこられた方なら、毎月お給料が振り込まれるのが当たり前の生活でした。それが年金だけになると、急に収入が減ってしまうように感じて、心細くなってしまうのですよね。
もし大きな病気や介護が必要になったら…という金銭的懸念
お一人での暮らしの中で、最も心配事の一つが健康の問題ではないでしょうか。今は元気でも、この先、大きな病気で入院したり、誰かの助けが必要になったりする可能性は誰にでもあります。
そうなった時、一体いくらかかるのだろう。貯蓄だけで足りるのだろうか。そして何より、「大切に思う息子家族にだけは、金銭的な負担をかけたくない」というその強いお気持ちが、不安をさらに大きくしているのかもしれません。ご自身の力でしっかりと備えておきたい、そう思うのはごく自然なことです。
周りと比べて焦る気持ち、誰に相談すれば良いのでしょうか
ご友人との何気ない会話で、NISAやiDeCoといった資産運用の話が出ると、「自分だけが何も準備できていないんじゃ…」と感じて、焦ってしまうことはありませんか?
「何か始めなくちゃ」と思いつつも、何から手をつけていいのか分からない。かといって、銀行や証券会社に相談に行くのは少し敷居が高い気がするし、身近に心から信頼して相談できる相手もいない…。そんな誰にも話せない孤独感も、不安を大きくする一因になっているのかもしれません。
昔入った保険、今の私に本当に合っているのかしら?
「保険は、万が一の時のお守りのようなもの」そう思って、大切な書類入れの奥にしまったままになっていませんか?ご主人様が亡くなられた時や、お子様がまだ小さかった頃に入った生命保険。それを今も続けている方は、実は少なくありません。
けれども、保険はライフステージの変化に合わせて見直すことがとても大切です。
- お子様が独立された今、もしもの時の大きな保障は本当に必要でしょうか?
- 最近の医療の進歩に、今の保険の保障内容は合っていますか?
- もしかしたら、もっと保険料を抑えて、その分を貯蓄やご自身の楽しみに回せるかもしれません。
「よく分からないから、とりあえずそのままにしている」という状態が、実は知らず知らずのうちに家計を圧迫し、将来への不安の種になっている可能性があるのです。
月20万円生活を実現する!今日から始める5つのステップ
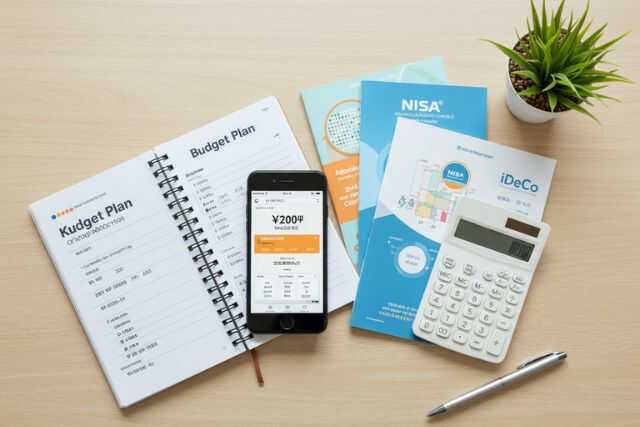
漠然としていた不安の正体が見えてきたら、今度はそれを一つひとつ「安心」に変えていく番です。ここからは、具体的な行動へと繋げるための5つのステップをご紹介します。難しいことはありませんから、ご自身のペースで、できることから一緒に始めてみましょう。
【ステップ1】リアルな生活費の内訳をシミュレーション
まずは、「月20万円」という予算の中で、どんな暮らしができるのかを具体的にイメージしてみましょう。週末に好きな読書やガーデニングを楽しむ時間を思い浮かべながら、ご自身の生活に合わせて調整してみてください。
| 費目 | 金額(目安) | 内容 |
|---|---|---|
| 住居費 | 60,000円 | 家賃や管理費、固定資産税など |
| 食費 | 40,000円 | 自炊中心で、たまに外食を楽しむ |
| 光熱・水道費 | 15,000円 | 電気・ガス・水道料金 |
| 通信費 | 5,000円 | 格安SIMの活用などで節約 |
| 保健医療費 | 10,000円 | 持病の薬代や定期的な通院費 |
| 趣味・娯楽費 | 20,000円 | 読書やガーデニング、友人とのランチなど |
| 交際費・雑費 | 20,000円 | 冠婚葬祭、日用品の購入など |
| 予備費(貯蓄) | 30,000円 | 将来の医療費や介護費、旅行などに備える |
| 合計 | 200,000円 |
この中で一番大切なのが、「予備費(貯蓄)」をしっかり確保すること。このお金があるという事実だけで、日々の暮らしの心の余裕が大きく変わってきます。
【ステップ2】通信費や光熱費など固定費を賢く削減する方法
毎月の支出を減らす上で、実は一番効果的なのが「固定費」の見直しです。一度だけ少し頑張って手続きをすれば、その節約効果がずっと続いていくのが嬉しいポイントですね。
- 通信費の見直し
- 大手キャリアから格安SIMに乗り換えるだけで、月々のスマホ代が驚くほど安くなることも。最近は手続きもずっと簡単になりました。
- 光熱費の見直し
- 電力会社やガス会社も、今は自由に選べる時代です。インターネットで簡単に比較シミュレーションをしてみるのも一つの方法です。
- 保険料の見直し
- 先に触れた通り、保険は大きな固定費の一つです。保障内容を今の暮らしに合わせて最適化することで、月々の負担を大きく減らせる可能性があります。
【ステップ3】NISAやiDeCoで「お金に働いてもらう」新習慣
「投資」と聞くと、少し怖いイメージが先に立ってしまうかもしれませんね。けれども、国が用意してくれているNISAやiDeCoといった制度は、老後の資金作りを応援してくれる、とても心強い味方です。
それはまるで、お庭に一本、果物の苗木を植えるようなもの。毎月少しずつお水をあげるように、少額からコツコツと積立てていくと、すぐには変わらなくても、長い時間をかけてやがて豊かな実りをもたらしてくれます。大切なのは、物価の上昇に負けないよう、お金の置き場所を少しだけ工夫してあげる、という視点です。
【ステップ4】公的年金の「繰下げ受給」という選択肢を知る
あまり知られていませんが、公的年金は受け取り始める年齢を遅らせる「繰下げ受給」という方法があります。65歳からすぐに受け取らず、66歳から75歳までの間で開始時期を遅らせることで、受け取れる年金額を増やせるのです。
| 受給開始年齢 | 増額率 |
|---|---|
| 66歳 | 8.4% |
| 70歳 | 42.0% |
| 75歳 | 84.0% |
※増額率は生涯変わりません。
もし65歳以降も少し働く予定がある、あるいは貯蓄に比較的余裕があるという方にとっては、将来の安定収入を大きく増やすことができる、とても心強い選択肢になるでしょう。
【ステップ5】予期せぬ出費に備えるための保険の見直し方
そして最後のステップが、将来の最大のリスクである「病気」や「介護」に備えるための保険の見直しです。今の医療事情に合わない古い保険のままでは、いざという時に入院給付金が少なかったり、先進医療に対応できなかったりするかもしれません。
かといって、不安な気持ちからやみくもに新しい保険に入るのは禁物です。まずは専門家に相談して、「今の自分に本当に必要な保障は何か」「貯蓄で備える部分と保険で備える部分をどう分けるか」を客観的に判断してもらうことが何より重要です。今の自分にぴったりの保険を見直すことは、未来の自分への最大の贈り物と言えるかもしれません。
住まいで支出は大きく変わる。持ち家と賃貸のメリット比較

日々の節約を地道に頑張っていても、大きな支出が一つあるだけで家計は大きく変わってしまいます。その代表格が、やはり「住居費」です。現在のお住まいの状況によって、将来のお金の流れは大きく変わりますから、ここで一度、「持ち家」と「賃貸」それぞれのこれからを考えてみましょう。
持ち家の場合にかかる固定資産税や将来の修繕費
住宅ローンを完済した持ち家にお住まいだと、月々の家賃負担がないため、やはり大きな安心感がありますよね。住み慣れた地域で、これからも穏やかに暮らしていきたいとお考えのことでしょう。
ただし、持ち家だからといって住居に関する費用が全くかからなくなるわけではありません。つい見落としがちなのが、以下の2つのコストです。
- 固定資産税・都市計画税:これは毎年必ずかかってくる費用です。
- 修繕費:外壁の塗り替えや給湯器の交換、水回りのリフォームなど、10年〜15年単位でまとまった出費が必要になってきます。
これらの費用をあらかじめ計画的に準備しておかないと、突然の出費で大切な貯蓄を大きく取り崩すことにもなりかねません。
賃貸で暮らし続ける場合の家賃と更新料のリアル
一方で、賃貸住宅の最大のメリットは、その身軽さにあると言えるでしょう。固定資産税や修繕費の心配がなく、ライフステージの変化に合わせて住み替えやすいという利点があります。
しかし、老後の暮らしを考えた時には、以下の点を心に留めておく必要があります。
- 家賃の支払いがずっと続く:年金が主な収入源となる中で、毎月決まった額の家賃を払い続けるのは、決して小さな負担ではありません。
- 契約更新の問題:残念ながら、高齢になると保証人の問題などで新しい賃貸契約が難しくなるケースもあります。
- 更新料の発生:2年に一度など、家賃とは別にまとまった費用が必要になることも忘れてはいけません。
どちらが良い・悪いという話ではなく、それぞれの特徴をよく理解した上で、ご自身のライフプランに合った選択をすることが大切なのです。
「月15万円」で暮らす場合の節約重視の生活モデル
もし収入が月15万円だった場合、暮らしはどう変わるのでしょうか。先ほどのシミュレーションから5万円を削る必要があるため、特に「趣味・娯楽費」や「交際費」、そして将来への「予備費」を大きく諦めることになります。
日々のささやかな楽しみや友人との付き合いを控え、将来への貯蓄もほとんどできないとなると、生活に潤いがなくなり、心が少し窮屈に感じられてしまうかもしれません。このことからも、月20万円という目標がいかに大切かが見えてきます。
「ゆとりある老後」を目指すならプラスいくら必要か
ある調査によると、経済的に「ゆとりある老後」を送るためには、最低限の生活費に加えて月々10万円〜15万円ほどの上乗せが必要だと考える方が多いようです。
その「ゆとり」の使い道で最も多いのが、「旅行やレジャー」なのだとか。年に一度は温泉旅行を楽しんだり、好きな趣味の教室に通ったり、あるいはお孫さんに素敵なプレゼントを買ってあげたり…。そんな心豊かな時間を過ごすためには、やはりある程度の経済的な余裕が欲しくなりますよね。月20万円の生活は、その「ゆとり」を生み出すための、かけがえのない土台となるのです。
老後の一人暮らしで気になるお金のこと、3つのQ&A

ここまで具体的なお話をしてきましたが、きっとまだ「こういう場合はどうなの?」という小さな疑問が心の中に残っているかもしれませんね。最後に、多くの方が共通して疑問に思われる点について、簡単にお答えします。
Q. 65歳以上の一人暮らしの平均年金受給額は?
A. 厚生労働省のデータによりますと、2022年度の厚生年金(国民年金含む)の平均受給額は月額で約14.4万円です。また、自営業などで国民年金のみに加入していた場合の平均は月額約5.6万円となっています。これらはあくまで全体の平均値で、現役時代の収入や加入期間で大きく個人差が出ますので、ご自身の「ねんきん定期便」で確認するのが一番確実です。
※出典:厚生労働省「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
Q. 老後資金は全体でいくら準備すれば安心ですか?
A. 「2000万円必要」など色々な情報がありますが、一概には言えません。一番大切なのは、ご自身の年金収入と、目標とする生活費(例えば月20万円)との「差額」をご自身で計算してみることです。
例えば、年金が月14万円で生活費が月20万円なら、毎月6万円が不足します。この6万円を貯蓄で補うとして、老後の期間を25年(300ヶ月)と仮定すると、「6万円 × 300ヶ月 = 1,800万円」が、まず一つの目安になります。これに加えて、万が一の医療費や介護費のための予備費を数百万円用意しておくと、より心穏やかに過ごせるでしょう。
Q. お金の専門家にはどんなことを相談できますか?
A. ファイナンシャル・プランナー(FP)などの専門家は、いわば「家計のホームドクター」のような存在です。ご自身一人では判断が難しい、以下のようなことを気軽に相談できますよ。
- 我が家のキャッシュフロー(お金の流れ)の現状分析と改善のヒント
- NISAやiDeCoなど、自分に合った資産形成方法のアドバイス
- 年金や高額療養費制度といった、使える公的制度の活用法
- 今の自分に本当に必要な保険の見極めと、無駄な保険料のカット
専門家の客観的な視点が入ることで、頭の中で漠然としていた不安が整理されて、次に何をすべきかがはっきりと見えてきます。
漠然とした不安を安心に。豊かな老後への最後の一歩

長い時間お付き合いいただき、本当にありがとうございます。老後のお金について真剣に考えることは、未来の自分を大切にする、とても前向きで素敵な作業です。
本記事の要点まとめ:月20万円生活は夢ではありません
最後に、この記事でお伝えした大切なポイントを、もう一度だけ振り返ってみましょう。
- 月20万円での一人暮らしは、計画的な準備で十分に実現可能です。
- まず現状を把握し、固定費、特に保険料の見直しから始めてみませんか。
- NISAや年金の繰下げ受給など、使える制度を賢く活用する方法もあります。
- 住まいのコストは、長期的な視点で考えることが大切です。
一つひとつのステップは、決して難しいものではなかったはずです。
一人で悩まず専門家を頼るという選択肢も大切です
それでも、いざ一人で全てを判断し、実行に移すのは心細いものですよね。そんな時は、どうぞ一人で抱え込まないでください。特に、ご自身の状況に合った保険の備えは、お金のプロと話すことで驚くほど明確になります。
「保険見直しラボ」の無料相談などを活用し、一度専門家の客観的なアドバイスを聞いてみてはいかがでしょうか。
さあ、今日から未来のために具体的な行動を始めましょう
漠然とした不安の正体は、多くの場合「分からないこと」です。しかし、この記事をここまで読んでくださったあなたは、もう昨日とは違います。何をすれば良いのか、その道筋が、ぼんやりとでも見え始めたのではないでしょうか。
未来は誰にも予測できません。けれども、今から備えることで、心の平穏はきっと手に入ります。あなたのこれからの人生が、お金の不安から解放され、あなたらしい豊かな時間で満たされることを、心から願っています。
