50代を迎え、老後の生活費は夫婦でリアルにいくら必要か、漠然とした不安を感じていませんか?この記事を読めば、公的データに基づいた生活費の内訳と、ご自身の状況に合わせた必要額を把握し、今すぐ始められる具体的な対策が分かります。
【忙しい方へ:要点まとめ】老後の夫婦の生活費は、暮らしのレベルによって大きく変わります。まず、この目安となる金額を把握することが、計画の第一歩です。
| 生活レベル | 夫婦2人の月額費用の目安 | 年金収入との差(モデルケース) |
|---|---|---|
| 最低限の日常生活 | 約23.2万円 | ▲ 約1.2万円の赤字 |
| ゆとりある生活 | 約37.9万円 | ▲ 約15.9万円の赤字 |
※生命保険文化センター「2022年度 生活保障に関する調査」、総務省「家計調査報告(家計収支編)2023年」を基に算出。年金収入は厚生労働省発表のモデル世帯(夫が厚生年金、妻が国民年金)の約22万円で計算。
夫婦の老後、生活費のリアルな実態と今からできる備えは?

長年お仕事を頑張ってこられた分、これからのご夫婦の時間は大切にしたい。そう考えるのは、ごく自然なことですよね。ここでは、その大切な時間を安心して過ごすための、お金のリアルな実態に迫ります。
この記事で分かること
- 公的データに基づくリアルな生活費の内訳
- ご家庭の状況に合わせた必要額のシミュレーション方法
- 50代からでも間に合う、具体的な5つの対策
- 将来の医療や介護リスクへの賢い備え方
年金だけでは「ゆとりある老後」は難しいという現実
まず、現実的な視点を持つことが大切です。厚生労働省が示すモデル世帯(夫が会社員、妻が専業主婦)の場合、受け取れる年金は月額で約22万円ほど。一方で、先に示した通り、最低限の日常生活費ですら月額23.2万円が必要というデータがあり、この時点で毎月1.2万円ほどの赤字となってしまいます。
ALTテキスト: 夫婦二人の老後の生活費と年金収入のギャップを示す棒グラフ。年金収入約22万円に対し、最低生活費約23万円、ゆとりある生活費約38万円が必要であることを示している。
もし、趣味の家庭菜園や年に数回の旅行も楽しむような「ゆとりある老後」を目指すのであれば、不足額はさらに大きくなります。だからこそ、年金はあくまで生活の土台と考え、豊かなセカンドライフをご自身で計画的に準備することが、今、求められているのです。
50代からの資金準備が老後の安心を左右する理由
「もう50代だから遅いのでは…」と感じる必要は全くありません。むしろ、50代は老後資金準備のラストスパートであり、ゴールデンタイムです。お子様が独立され、教育費の負担が軽くなるご家庭も多いのではないでしょうか。退職までの期間と退職金というまとまった資金が見えている今だからこそ、非常に現実的な計画を立てやすい時期と言えます。
これからの10年ほどの期間で、家計を見直し、賢く備える。その行動が、65歳以降の生活の質を大きく、そして豊かに変えていきます。不安を感じている今こそ、行動を起こす絶好のタイミングなのです。
「本当に足りる?」漠然とした老後資金への3つの不安
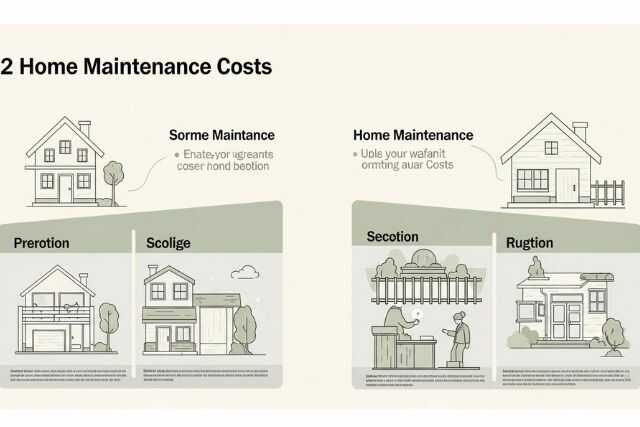
同年代のご友人の話などを聞くと、ふと「自分たちの場合は大丈夫だろうか」と、胸のあたりが少しざわつく…。そのお気持ち、よく分かります。ここでは、多くの方が抱える3つの具体的な不安を、一つひとつ解きほぐしていきましょう。
悩み1:平均額では分からない「我が家のリアルな生活費」
「老後資金2,000万円問題」という言葉を耳にして、不安が大きくなった方もいらっしゃるでしょう。しかし、あの数字はあくまで特定のモデルケースを基にした平均値に過ぎません。大切なのは、平均額に一喜一憂することではなく、ご自身のライフスタイルに合った「我が家のリアルな生活費」を、ご自身のものさしで測ることです。
週末の過ごし方、交際費、食生活のこだわりなど、お金のかけ方はご家庭によって全く異なります。この記事の後半では、ご自身の価値観を反映した生活費をシミュレーションする方法を具体的に解説しますので、ご安心ください。他人事の数字ではなく、自分事として考えることが、不安解消への確かな一歩となります。
悩み2:持ち家でもかかる想定外の出費とは?
住宅ローンを完済した持ち家があれば、家賃の心配がなく安心だと考えがちです。たしかにその通りですが、住居関連の費用がゼロになるわけではありません。むしろ、暮らしの中でじわじわとかかる、見過ごしがちな出費が存在するのです。
| 項目 | 内容と目安 |
|---|---|
| 固定資産税・都市計画税 | 自治体や評価額によるが、年間10〜15万円程度が一般的。 |
| 修繕・リフォーム費用 | 築年数と共に、外壁塗装や水回りの修繕は必須。10〜15年周期で100万円単位の費用が発生することも。 |
| 火災保険・地震保険料 | 補償内容によるが、5年契約などで数万円〜十数万円の更新費用がかかる。 |
| バリアフリー化費用 | 将来の身体状況に合わせ、手すりの設置や段差解消のリフォームが必要になる可能性がある。 |
これらの費用は、毎月の生活費とは別に、ある時まとまって必要になるもの。あらかじめ計画に織り込んでおくことがとても重要です。
悩み3:一番心配な病気や介護への備えは十分か
多くの方が最も大きな不安を感じるのが、ご自身やパートナーの健康問題ではないでしょうか。特に、身近な方の入院といった話を聞くと、その不安は一気に現実味を帯びてきます。厚生労働省の調査によると、健康的に過ごせる「健康寿命」と平均寿命の間には、男性で約9年、女性で約12年もの差があるのが実情です。
(出典:厚生労働省「健康寿命の令和元年値について」)
この期間は、何らかの医療や介護のサポートが必要になる可能性が高い時期を意味します。
- 先進医療など、公的保険適用外の治療を受ける可能性
- 介護施設への入居費用(一時金や月額利用料)
- 在宅介護サービス利用時の自己負担額
これらの費用は、時に数百万円単位になることも珍しくありません。現在の貯蓄や保険だけで、こうした万が一の事態に本当に対応できるのか、一度立ち止まって冷静に確認しておく必要があります。
50代から始める!夫婦の老後資金、不安を解消する5ステップ
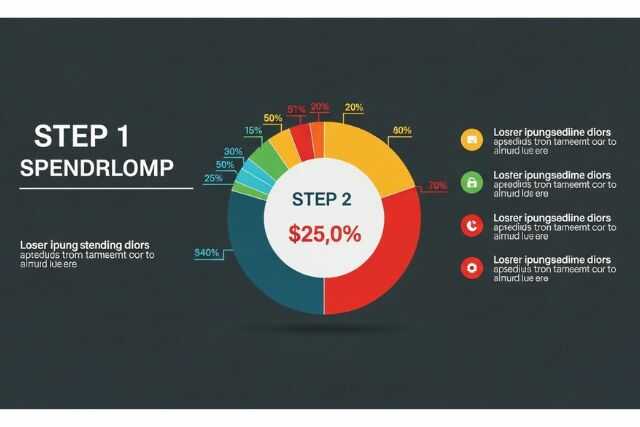
具体的な数字が見えてくると、少し気が重くなるかもしれません。でも、ご安心ください。ここからは、その不安を具体的な行動に変えるための、5つのステップをご紹介します。
Step1:データで知る!老後の生活費、そのリアルな内訳
まずは、一般的な高齢者無職世帯(夫婦2人)が、何にいくら使っているのか、具体的なデータを見てみましょう。これは、ご自身の生活費を考える上での「ものさし」として役立ちます。
| 費目 | 金額(月額) | 概要 |
|---|---|---|
| 食料 | 72,930円 | 日々の食費。外食なども含む。 |
| 住居 | 16,827円 | 持ち家世帯が多いため平均は低いが、修繕費や税金は別途考慮。 |
| 光熱・水道 | 22,422円 | 電気、ガス、水道料金。 |
| 保健医療 | 16,879円 | 病院の診察代、薬代、健康維持費など。 |
| 交通・通信 | 30,729円 | 公共交通機関、ガソリン代、スマホ・ネット料金など。 |
| 教養娯楽 | 24,690円 | 趣味、旅行、習い事など、生活の潤いに関わる費用。 |
| その他(交際費など) | 50,839円 | 親戚付き合い、友人との交流、冠婚葬祭、雑費など。 |
| 合計(消費支出) | 250,959円 |
※総務省「家計調査報告(家計収支編)2023年」65歳以上の夫婦のみの無職世帯のデータを基に作成
この表を見て、「うちは食費がもっとかかりそう」「教養娯楽はもう少し抑えられるかな」といったように、ご自身の生活と照らし合わせてみることが大切です。
Step2:我が家の場合は?簡単シミュレーションで必要額を把握
それでは、いよいよ「我が家」のケースを考えてみましょう。複雑な計算は不要です。以下の3つのステップで、おおよその必要額が見えてきます。
- 現在の生活費を書き出す
家計簿を参考に、現在の毎月の支出を費目ごとに書き出します。「今の生活」を基準に考えるのがポイントです。 - 老後をイメージして金額を調整する 書き出した項目を見ながら、「老後はどうなるか」を想像して金額を増減させます。
- 減る可能性のある支出: 住宅ローン、生命保険料(払込満了後)、子供関連費
- 増える可能性のある支出: 保健医療費、夫婦での旅行・娯楽費、交際費
- 年金収入を差し引く
毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」や、日本年金機構の「ねんきんネット」で、将来受け取れる年金額の見込みを確認します。②で算出した「老後の予想生活費」から、年金収入を差し引いた額が、毎月ご自身で準備すべき金額の目安となります。
このシミュレーションで、漠然としていた不安が「毎月あと〇万円」という具体的な目標に変わるはずです。
Step3:見えた不足額にどう備える?家計見直しのポイント
シミュレーションで不足額が見えたとしても、決して落ち込む必要はありません。退職までの時間は、まだ十分にあります。家計の見直しは、いわば家の健康診断のようなもの。どこを改善すれば、より健全になるかを見つける作業です。
- 固定費の見直し(効果が大きい)
- 通信費: スマートフォンの料金プランは、本当に今のままで最適ですか?格安SIMへの乗り換えも検討の価値ありです。
- 保険料: 加入したままになっている保険はありませんか?保障内容が現在のライフステージに合っているか、定期的な確認が不可欠です。
- 光熱費: 電力・ガス会社は自由化されています。よりお得なプランがないか比較してみるのも良いでしょう。
- 変動費の見直し(意識改革が重要)
- 食費: 外食の回数を少し減らし、夫婦で料理を楽しむ時間を増やすのも一つの方法です。
- 交際費: 現役時代のお付き合いも、定年後は少しずつ見直していく必要があるかもしれません。
無理な節約は長続きしません。まずは一つでも、効果が大きく、続けやすい固定費の見直しから着手するのが成功のコツです。
Step4:固定費削減だけじゃない!資産寿命を延ばす考え方
支出を減らす「守り」の発想と同時に、今ある資産を賢く活用して長持ちさせる「攻め」の発想も大切になります。これを「資産寿命を延ばす」と言います。50代からでも始められる方法は、意外と多く存在します。
- 働く期間を延ばす
近年は、65歳以降も継続雇用や再雇用で働く環境が整っています。年金受給開始までの収入を確保するだけでなく、健康維持や社会との繋がりを持つ意味でも非常に有効な選択肢です。 - 退職金の賢い活用
まとまった退職金を、ただ普通預金に預けておくだけではインフレで価値が目減りする恐れがあります。NISAなどを活用し、リスクを抑えながら一部を運用に回すことで、資産に「働いてもらう」ことも検討してみてはいかがでしょうか。 - 年金の繰下げ受給
もし65歳以降も収入があり、すぐに年金を受け取る必要がなければ、「繰下げ受給」を検討するのも一手です。受給開始を1ヶ月遅らせるごとに年金額が0.7%増え、75歳まで繰り下げると最大で84%も増額されます。
これらの選択肢を組み合わせることで、家計の安定度は格段に向上します。
Step5:医療・介護費に備える「保険の見直し」という賢い選択
これまで様々な対策を見てきましたが、老後の不安要因として最後まで残るのが、いつ、いくらかかるか予測が難しい「医療費」と「介護費」です。この最大のリスクに、真正面から備えるために最も合理的な手段が「保険の見直し」なのです。
50代は、保険を見直す最後のチャンスとも言える大切な時期です。
- 保障内容の確認: お子様が独立した今、万が一の時の高額な死亡保障は本当に必要ですか?その分を、これからの医療保障や介護保障に手厚く振り分けるべきかもしれません。
- 先進医療への備え: 公的保険が適用されない先進医療の技術料は、数百万円に及ぶこともあります。特約で備えられているか確認しておきましょう。
- 介護状態の定義: 「要介護2以上で給付」など、ご自身の保険がどのような状態になった時に支払われるのか、正確に把握していますか?
若い頃に加入した保険のままでは、現在の医療事情やご自身のライフステージに合っていない可能性が非常に高いのです。専門家のアドバイスを受けながら、今の自分たちに本当に必要な保障は何かを再設計することが、将来の揺るぎない安心に直結します。
【FAQ】夫婦の老後生活費について、よくある3つの疑問
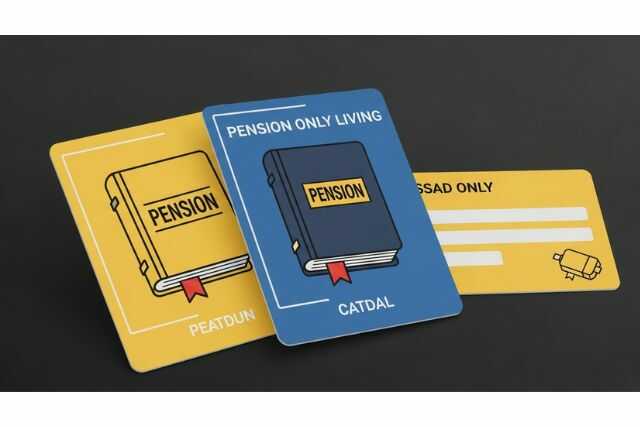
Q1. 老後2000万円問題って、結局いくら必要なんですか?
A1. 「2000万円」という数字は、2019年に金融庁が公表した報告書にある「高齢夫婦無職世帯では毎月約5.5万円の赤字が生じ、30年間で約2000万円の取り崩しが必要になる」という試算が基になっています。これはあくまで特定の前提に基づく一例です。必要な金額は、本記事で解説したように、ご自身の年金受給額や目指す生活レベルによって大きく異なります。数字に惑わされず、ご自身の状況でシミュレーションすることが何よりも重要です。
Q2. 夫婦の年金だけで生活するのは可能ですか?
A2. 理論上は可能ですが、生活レベルをかなり切り詰める必要があります。先のデータで示した通り、モデル世帯の年金収入(月約22万円)では、最低限の生活費(月約23.2万円)にも届かないのが現状です。持ち家の修繕費や医療費、冠婚葬祭などの臨時出費を考慮すると、年金収入だけでやりくりするのはかなり厳しいと言わざるを得ません。ある程度の貯蓄を取り崩しながら生活するのが現実的でしょう。
Q3. 退職金は老後資金として、どのように考えれば良いですか?
A3. 退職金は、老後資金の非常に重要な柱です。しかし、「退職金があるから安心だ」と考えるのは少し早いかもしれません。まずはご自身の会社の退職金規程を確認し、おおよその支給額を把握しましょう。その上で、全額を生活費の補填に充てるのではなく、一部を「住宅リフォーム用」、一部を「介護・医療用」、そして一部を「資産運用用」といったように、目的別に分けて計画を立てることをお勧めします。
まとめ:不安な今こそ、夫婦で未来を計画する第一歩を

【総まとめ】夫婦で豊かな老後を送るための要点
これまで見てきたように、老後の生活費に対する漠然とした不安は、一つひとつ手順を踏むことで、具体的な目標と計画に変えることができます。
- 老後の生活費は、最低でも月23万円、ゆとりを持つなら月38万円が目安。
- 年金だけでは不足する可能性が高く、自助努力が不可欠。
- まずは「我が家のリアルな生活費」をシミュレーションし、現状を把握する。
- 不足額に対しては、「支出の見直し」と「資産寿命を延ばす」両面から対策する。
- 予測不能な医療・介護リスクには、50代での「保険の見直し」が最も有効な備えとなる。
大切なのは、不安な気持ちから目を背けず、ご夫婦で向き合い、今できることから始めることです。
ここまで読んで、「自分たちだけで計画を立てるのは難しそうだ」「保険の見直しと言っても、何から手をつければ…」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。ご安心ください。そんな時こそ、お金の専門家の力を借りるのが賢明な選択です。
「保険見直しラボ」のような無料相談サービスでは、数多くの保険商品の中から、ご家庭の状況や将来の希望に最も合ったプランを中立的な立場で提案してくれます。漠然とした不安を、専門家と一緒に具体的な安心に変える第一歩を、ぜひ踏み出してみてはいかがでしょうか。
