ご家族への大切な想いを、確実に、そして望む形で遺すために。遺言書への生命保険の書き方を、この機会に正しく理解しませんか。本記事では、相続の専門家が法的なポイントや「通知の競争」といった見落としがちなリスク、そして具体的な対策までを分かりやすく解説します。
【はじめに結論】遺言書による生命保険金の受取人変更は法律で認められていますが、元の受取人が先に保険会社へ請求した場合、そちらが優先されるという重大なリスクがあります。この「通知の競争」に負けないためには、以下の対策が極めて重要です。
| 項目 | 結論 |
|---|---|
| 遺言での受取人変更 | 可能(保険法第44条) |
| 最大のリスク | 契約上の受取人が先に請求すると、そちらが優先される |
| 最も確実な対策 | 公正証書遺言の作成+遺言執行者の指定 |
この記事で分かること
- 生命保険金が持つ「相続財産ではない」という法的な意味
- 良かれと思った遺言書が、かえって家族のトラブルを招く失敗例
- ご自身の想いを確実に実現するための具体的な5つのステップ
- 法的に最も安全で、無効になりにくい遺言書の形式と注意点
【最初に確認】遺言書での生命保険の書き方の基本ルール
定年を前に、ご家族の将来を考える時間が増えた今だからこそ、押さえておきたいことがあります。遺言書と生命保険の関係には、まず知っておくべき2つの法的な基本ルールが存在します。この原則を知らないままだと、意図しない結果を招く可能性があるため、最初に腑に落ちるまで理解しておくことが何より重要です。
生命保険金は「相続財産ではない」という大原則
まず最も大切なのは、死亡保険金は法律(民法)上、亡くなった方の「相続財産」には含まれないという点です。これは、保険金が保険契約に基づいて受取人に直接支払われる「受取人固有の財産」と見なされるためです。
この性質により、預貯金や不動産とは異なる、以下のような特徴が生まれます。
| 項目 | 民法上の扱い(遺産分割) | 相続税法上の扱い(税金計算) |
|---|---|---|
| 法的性質 | 受取人の固有財産 | みなし相続財産 |
| 遺産分割 | 対象外(相続人の話し合いは不要) | 課税対象(他の財産と合算) |
| 非課税枠 | なし | あり(500万円×法定相続人数) |
このように、遺産分割のルールと税金のルールとでは、生命保険金の扱いが全く異なることを、まずは心に留めておきましょう。
遺言による受取人変更は保険法で明確に認められている
かつては見解が分かれていましたが、平成22年に施行された保険法により、遺言書によって生命保険金の受取人を変更できることが法律で明確に定められました(保険法第44条)。これにより、ご自身の最終意思として、特定の誰かに保険金を遺すことが可能になったのです。
ただし、これには極めて重要な条件が付いています。それは、遺言書があるだけでは効力は完結せず、亡くなった後、相続人などが保険会社へ「遺言で受取人が変わりました」と通知して初めて、法的な効力が生じるという点です。この「通知義務」こそが、次の問題の根源となります。
遺言と保険契約、実際にはどちらが優先される?
「遺言」と「保険契約書」、どちらが強いのか。その答えは「先に行動した方が優先される」です。これは「通知の競争」とも呼ばれる、遺言による受取人変更における最大のリスクポイントにほかなりません。
これは例えるなら、銀行の窓口での手続き競争のようなものです。先に正しい書類を出した人が手続きを完了できるように、保険金も先に正当な権利者として請求した人に支払われてしまうのです。
- 遺言者が亡くなる
- 保険契約書上の受取人(元の受取人)が、すぐに死亡の事実を保険会社に伝え、保険金を請求する
- 保険会社は正当な請求として、元の受取人に保険金を支払う
- その後、遺言で指定された新しい受取人が、遺言書を持って保険会社に通知する
- しかし、保険会社はすでに支払義務を果たしているため、新しい受取人は保険金を受け取れない
この場合、新しい受取人は、お金を受け取った元の受取人に対して裁判を起こすしかなく、ご家族が深刻な紛争に巻き込まれてしまうのです。
「家族が揉めたら…」その不安、遺言書の作り方が原因かも

親御様の相続で心を痛めた経験がある方なら、なおさら「自分の家族だけは絶対に揉めさせたくない」と強くお考えのことでしょう。実は、法的なルールを知らないばかりに、その想いとは裏腹に、ご家族を悩ませてしまうケースは少なくありません。
「妻に全財産を」と書いても保険金は渡らないケースとは
遺言書でよく見られる「私の一切の財産を、妻〇〇に相続させる」という包括的な記述。これで万全だと思われがちですが、ここに思わぬ落とし穴があります。
先に述べた通り、生命保険金は「相続財産」ではありません。したがって、この「一切の財産」の中に、生命保険金は含まれないのです。もし保険契約の受取人がお子様になっていれば、遺言書の内容にかかわらず、保険金はお子様に支払われます。奥様の生活のためにと想っていても、その大切な意思が反映されない可能性があるため、注意が必要です。
子供たちへ公平に、が逆に争いの火種になってしまうことも
ご長男には事業資金を、ご長女には結婚資金を、とそれぞれに配慮した財産配分を考えるのは、素晴らしい親心ですよね。ところが、生命保険金の「相続財産ではない」という特性が、時として不公平感を生み、争いの原因になることがあります。
例えば、遺産の大半が生命保険で、特定の相続人のみが受取人に指定されている場合です。他の相続人から見れば、著しく不公平だと感じるのも無理はありません。こうしたケースでは、例外的に、生命保険金も遺産に含めて計算し直すべきだとして「遺留分」の侵害を主張される可能性があります。「遺留分」とは、法律で保障された相続人の最低限の取り分のことです。
良かれと思った自筆証書遺言が法的に無効になるリスク
費用をかけず手軽に作成できる自筆証書遺言ですが、法律で定められた厳格な要件を一つでも満たさないと、遺言書そのものが無効になってしまいます。
- よくある無効のパターン
- 日付が「令和7年9月吉日」のように特定できない
- 全文パソコンで作成してしまった(財産目録を除く)
- 押印を忘れている
- 訂正の仕方を間違えている
せっかくご家族のために遺した想いが、わずかな形式不備で水の泡となり、受取人変更の効力も失われてしまう。これほど悲しいことはありません。
揉めない相続へ!生命保険を遺言書に記すための5ステップ
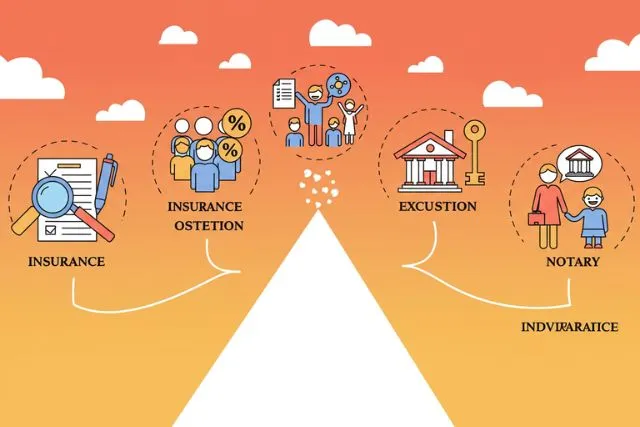
不安な点を洗い出したら、次はいよいよ具体的な対策です。どうすればご自身の意思を確実に実現し、円満な相続へと繋げられるのでしょうか。ここでは、専門家の視点から、実行すべき具体的な5つのステップに沿って解説します。この手順通りに進めることが、失敗しないための鍵となります。
STEP1:加入中の全保険契約の内容を正確に把握する
まず初めに取り組むべきは、現状の把握です。ご自身が加入している生命保険の保険証券をすべて手元に集め、以下の情報を一覧表などに正確に書き出してみてください。この作業が、すべての計画の土台となります。
- 保険会社名
- 保険証券番号
- 保険の種類(終身保険、定期保険など)
- 現在の保険金受取人
- 死亡保険金額
このリストアップを通じて、どの契約の受取人を、誰に変更したいのかを明確にしていきます。
STEP2:保険契約を特定できる情報を漏れなく記載する
遺言書に受取人変更の意思を記す際は、どの保険契約について述べているのか、誰が見ても一意に特定できるように具体的に記載する必要があります。曖昧な表現は、後日のトラブルの原因となるため、ここは慎重に進めましょう。
| 記載必須項目 | 記載例 |
|---|---|
| 保険会社名 | 〇〇生命保険株式会社 |
| 保険証券番号 | 第123456789号 |
| 保険の種類など | 終身保険(契約者・被保険者:鈴木正雄) |
最低でも上記の3点は、保険証券を見ながら正確に転記することが求められます。
STEP3:新しい受取人とその取得割合を明確に指定しよう
次に、誰を新しい受取人にするのかを明記します。ここでも、客観的に個人を特定できるように、氏名、続柄、生年月日を正確に記載することが望ましいです。
また、複数の人を受取人に指定する場合は、それぞれの取得割合まで必ず指定してください。「長男と長女に」とだけ書くと、半分ずつなのか、あるいは別の割合なのかで解釈が分かれ、争いになりかねません。「長男〇〇に3分の2、長女△△に3分の1の割合で」といった形ではっきりと示しましょう。
STEP4:「遺言執行者」を指定して通知義務を確実に託す
これが最も重要な戦略的ポイントです。「通知の競争」に負けないために、遺言執行者を指定しましょう。遺言執行者とは、いわば、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う権限を与えられた代理人です。
遺言執行者がいれば、相続人全員の同意や協力を待つことなく、単独かつ迅速に保険会社へ受取人変更の通知を行えます。もし指定がないと、元の受取人である相続人が手続きを妨害する可能性も否定できません。ご自身の意思を貫徹するための、いわば「切り札」となる存在なのです。
STEP5:法的安定性の高い公正証書遺言という選択肢
自筆証書遺言の無効リスクを避け、ご自身の想いを最も確実な形で遺すためには、公証役場で作成する「公正証書遺言」を選択することが最善策と言えます。
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成に関与するため、形式不備で無効になる心配がほぼありません。また、遺言者の意思能力も確認されるため、後から「無理やり書かされたのでは」といった疑義が生じにくく、紛争予防効果が非常に高いのが特徴です。作成に費用と手間はかかりますが、それを補って余りある安心感が得られます。
【ケース別】成功例と失敗例から学ぶ遺言書の注意点

「百聞は一見に如かず」と言います。理論だけでなく、具体的な事例を知ることで、リスクをより現実的に捉え、対策の重要性を実感できるはずです。ここでは、実際に起こりうる3つのケースを見ていきましょう。
成功例:遺言執行者の活躍で故人の意思を完璧に実現
障がいを持つ長男の将来を案じた父親が、受取人を妻から長男へ変更する旨を公正証書遺言に記したケースです。この父親は、遺言執行者として司法書士を指定し、生前にその任務をしっかりと伝えていました。
父親の死後、遺言執行者である司法書士は直ちに手続きに着手。他の相続人の協力を必要とせず、迅速に保険会社へ通知と請求を行いました。結果、保険金は速やかに長男の口座へ振り込まれ、父親の最後の想いは、争いなく完璧に実現されたのです。
失敗例①:「通知の競争」に敗れて遺言が無力化する悲劇
長年介護をしてくれた長男に感謝し、受取人を疎遠だった長女から長男へ変更する有効な遺言書を遺した父親のケース。しかし、父親の死後、長男は悲しみと葬儀などの多忙で、保険会社への連絡が10日ほど遅れてしまいました。
その間に、自分が受取人であることを知っていた長女は、死亡後わずか3日で保険金を請求。保険会社は正当な請求として支払い、その後に長男が遺言書を提示しても、時すでに遅し。遺言は事実上無力化し、家族は骨肉の争いへと発展してしまいました。
失敗例②:形式不備で自筆証言遺言が無効になるケース
再婚した母親が、保険金の受取人を現在の夫から、前夫との子である息子へ変更したいと考え、自筆で遺言書を作成したケースです。しかし、作成日付を「令和七年九月吉日」と曖昧に記載し、保険証券番号も書き間違えていました。
母親の死後、家庭裁判所での検認手続きにおいて、この遺言書は日付が特定できないため形式不備で「無効」と判断されました。受取人変更は一切効力を生じず、保険金はすべて契約上の受取人である夫が受け取ることになり、息子の権利は認められませんでした。
注意点:遺留分を侵害し、新たな火種を作らないために
生命保険は、特定の相続人に多くの財産を渡したい場合に有効な手段ですが、やりすぎは禁物です。保険金が遺産総額に対してあまりに高額だと、他の相続人から「不公平すぎる」として遺留分侵害を主張されるリスクがあります。
| 相続人の組み合わせ | 全体の遺留分 |
|---|---|
| 配偶者のみ | 法定相続分の1/2 |
| 子のみ | 法定相続分の1/2 |
| 配偶者と子 | 法定相続分の1/2 |
| 直系尊属(親など)のみ | 法定相続分の1/3 |
遺言を作成する際は、財産全体のバランスを考慮し、他の相続人の遺留分を不当に侵害していないか、という視点を持つことが、後の紛争を防ぐ上で非常に重要です。
遺言書と生命保険に関するよくある質問(FAQ)

さて、ここまで読み進めていただいた方からよく寄せられる質問があります。ご自身の状況と照らし合わせながら、最後の疑問点を解消していきましょう。
Q. 相続放棄をしても生命保険金は受け取れますか?
A. はい、受け取れます。
生命保険金は受取人固有の財産であり、相続財産ではないためです。したがって、亡くなった方に多額の借金があり、家庭裁判所で相続放棄の手続きをした場合でも、ご自身が受取人に指定されていれば、その保険金を受け取ることは可能です。ただし、相続人ではなくなるため、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)は適用できなくなる点に注意が必要です。
Q. 遺言で指定した受取人が先に亡くなったらどうなる?
A. 遺言による受取人変更の指定は効力を失い、元の受取人に戻る、あるいは法定相続人が受け取ることになります。
これは非常に複雑な問題です。このような事態を避けるためには、遺言書に「もし長男〇〇が私より先に死亡した場合は、長男の子である△△を受取人とする」といった形で、予備的な受取人を指定しておくことが有効な対策となります。
Q. 税金はどう変わる?「みなし相続財産」とは何ですか?
A. 相続人が受け取る限り、税金の種類(相続税)は変わりません。
「みなし相続財産」とは、相続税を計算する時だけ、相続財産とみなして課税対象に含める財産のことです。生命保険金は、亡くなったことを原因として受け取るため、実質的に相続と同じだと考えられているのです。これは課税の公平性を保つためのルールであり、遺産分割のルール(固有の財産)とは別物として理解することが大切です。
ここまでお読みいただき、ご自身のケースではどうすれば最善なのか、専門家へ具体的に相談したくなった方もいらっしゃるでしょう。弁護士や税理士は敷居が高いと感じるかもしれませんが、まずは保険と資産の専門家であるFP(ファイナンシャル・プランナー)に、気軽に話を聞いてみることから始めるのがおすすめです。
まとめ:専門家への相談が円満相続への第一歩です

本記事では、遺言書で生命保険の受取人を変更する方法と、その際に起こりうるリスク、そして確実にご自身の意思を伝えるための対策を、専門家の視点から解説しました。
あなたの想いを家族に正しく、そして確実に伝えるために
ご家族を想うからこそ、その気持ちが法的な手続きの不備によって、意図しない結果を招いてはなりません。正しい知識を身につけ、適切な準備をすることが、ご家族を守ることに直結します。
- 円満相続のためのキーポイント
- 生命保険は「受取人固有の財産」
- 「通知の競争」のリスクを理解する
- 「公正証書遺言」と「遺言執行者」が最強の組み合わせ
- 財産全体のバランスと「遺留分」への配慮
遺言書の作成と保険の見直しはセットで考えるのが最善策
遺言書で財産配分を考えることは、現在の保険内容がご自身の想いに合致しているかを見直す絶好の機会です。そもそも今の保険金額で十分なのか、受取人はそのままで良いのか、といった点も併せて確認することが、より万全な対策に繋がります。
まずは無料相談で専門家の話を聞いてみる
「自分の場合はどうなんだろう」「誰に相談すればいいかわからない」もし、そう感じているのであれば、まずは一歩踏み出して、専門家の意見を聞いてみてはいかがでしょうか。多くの保険商品を取り扱う相談サービスでは、中立的な立場で、ご自身の状況に合わせた最適なプランを提案してくれます。大切なご家族のために、今できることから始めてみましょう。
