大切な家族を失う経験は、言葉では言い尽くせないほどの悲しみと、その後の様々な手続きへの戸惑いをもたらします。特に葬儀後の対応は、心身ともに疲れている中で、マナーへの配慮も必要となり、不安を感じる方も少なくないでしょう。
このブログ「終活の窓口」では、終活やお墓に関する情報を通じて、皆さまが安心して人生の最終段階を迎えられるようサポートすることを目指しています。今回は、葬儀でいただいた弔電へのお礼、特に「口頭で伝える場合」に焦点を当てて、多くの方が抱える疑問や不安にお答えしていきます。
「会社の上司や同僚、近所の方など、直接会う機会がある方に口頭でお礼を伝えたいけれど、いつ、どんな言葉で伝えれば失礼にならないだろうか」「『ありがとうございました』だけでは不十分な気がする…」そんなお悩みはありませんか?
私自身の経験も踏まえ、弔電のお礼を口頭で伝える際の基本的なマナーから、具体的な例文、会社関係者への対応まで、分かりやすく解説していきます。この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、心を込めて感謝の気持ちを伝えるための一助となれば幸いです。
- 口頭でのお礼は可能ですが、タイミングと言葉遣いへの配慮は必須です。
- 感謝と葬儀終了報告を基本に、例文を参考に状況に応じた言葉を選びましょう。
- 会社関係者へは口頭が基本ですが、メール等の利用は慎重に判断してください。
- 最も大切なのは、マナーを踏まえつつ感謝の気持ちを誠実に伝えることです。
弔電のお礼を口頭で伝える際の基本マナーとタイミング
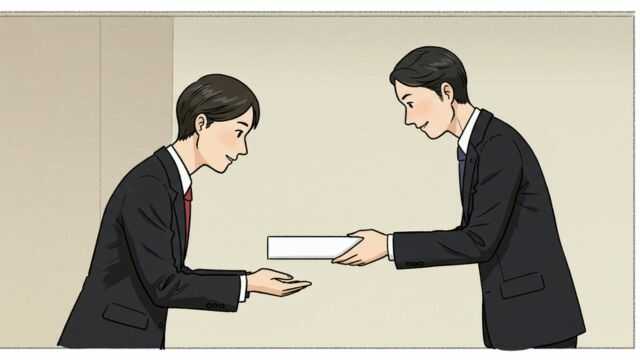
この記事で分かること
- 弔電のお礼を口頭で伝える際の基本的なマナーと適切なタイミング
- 相手や状況に応じた具体的なお礼の言葉・フレーズ(例文付き)
- 会社関係者(上司・同僚など)へのお礼の伝え方と注意点
- 電話やメール、LINEでのお礼は適切かどうかの判断基準
- 弔電のお礼に関するよくある質問(お返しの要否など)
弔電は、故人を悼み、遺族を気遣う温かい気持ちの表れです。いただいた弔意に対して、感謝の気持ちを伝えることは、遺族としての大切な務めの一つと言えるでしょう。特に口頭でお礼を伝える際には、タイミングや言葉遣いに心を配る必要があります。まずは、基本的なマナーとタイミングについて確認しましょう。
“今さら連絡したら失礼では…”と不安に思う方もいますが、気持ちを込めていれば決して失礼にはなりません。
弔電へのお礼はいつ、どのように伝えるのが基本?
弔電へのお礼は、葬儀後なるべく早く、できれば1週間以内に行うのが一般的な目安とされています。これは、弔電への感謝を伝えるだけでなく、葬儀が無事に終了したことを報告する意味合いも含まれているためです。(出典: 小さなお葬式)
万が一、様々な事情でお礼が目安の期間よりも遅れてしまった場合は、お詫びの言葉を一言添えるようにしましょう。「お礼が遅くなり、申し訳ございません」といった一言があるだけで、相手への配慮が伝わります。
基本的なお礼の方法としては、以下のものが挙げられます。
- 直接訪問: 相手の自宅や会社などを訪ねて直接お礼を伝える方法。
- お礼状(手紙・ハガキ): 書面でお礼を伝える方法。
- 電話: 電話で直接お礼を伝える方法。
どの方法を選ぶかは、相手との関係性や状況によって異なります。
お礼の方法:直接訪問・お礼状・電話の違いと選び方
弔電へのお礼を伝える方法はいくつかありますが、それぞれ丁寧さの度合いや適した状況が異なります。
- 直接訪問: 最も丁寧な方法とされています。相手の都合を確認した上で、葬儀後少し落ち着いてから、なるべく早い時期に伺うのが良いでしょう。
- お礼状(手紙・ハガキ): 近年、最も一般的になっている方法です。遠方の方や、直接会う機会が少ない方、フォーマルな関係の方へのお礼に適しています。手書きがより丁寧ですが、印刷でも問題ありません。
- 電話: 親しい間柄の親族や友人などに対しては、電話でお礼を伝えても失礼にはあたりません。お礼状よりも早く気持ちを伝えたい場合に適しています。ただし、電話は略式とみなされるため、「本来であれば直接お伺いすべきところですが」といった一言を添えるとより丁寧です。(出典: e-denpo, https://www.e-denpo.net/弔電のお礼状・お返しのマナーとは?はがきやメールでの/)
どの方法を選ぶかは、相手との関係性の深さを考慮して判断しましょう。例えば、頻繁に顔を合わせる会社の同僚や近所の方には口頭で伝え、遠方の親戚にはお礼状を送るといった使い分けが考えられます。
弔電のお礼を口頭で伝えるのに適したタイミングとは
口頭でお礼を伝える場合、タイミングが非常に重要です。失礼なく、かつ相手に負担をかけないタイミングを見計らいましょう。
- 直接訪問する場合: 相手の都合の良い日時を確認し、事前に連絡してから伺います。訪問時間は長居せず、手短にお礼を述べるのがマナーです。
- 電話の場合: 相手の都合が良い時間帯(早朝や深夜、食事時などを避ける)を選びましょう。葬儀の翌日など、なるべく早い段階で連絡するのが望ましいとされていますが、相手の状況も考慮してください。
- 会社関係者へ伝える場合: 忌引き休暇明けの出社日が最も一般的です。朝礼や業務開始前、あるいは個別に時間を取ってもらい、上司や同僚へ直接お礼を述べましょう。休み中の業務フォローへの感謝も合わせて伝えると良いでしょう。
- その他の場合(近所の方など): 日常的に顔を合わせる機会があれば、その際に「先日はありがとうございました」と一言添えるだけでも構いません。ただし、立ち話で長々とお礼を述べるのは避け、簡潔に伝えるようにしましょう。
いずれの場合も、相手の状況をよく見て、邪魔にならないタイミングを選ぶことが大切です。
口頭でのお礼とお礼状は両方必要?使い分けの考え方
「口頭でお礼を伝えたら、お礼状は送らなくてもいいの?」と迷う方もいらっしゃるかもしれません。
結論から言うと、口頭でお礼を伝えた場合でも、後日改めてお礼状を送るのが最も丁寧な対応とされています。特に目上の方や、今後も良好な関係を築きたい相手に対しては、両方行う方がより気持ちが伝わるでしょう。
しかし、相手との関係性や状況によっては、口頭でのお礼のみで済ませても必ずしもマナー違反とは限りません。例えば、
- 非常に親しい友人や同僚で、日頃から頻繁にコミュニケーションを取っている場合
- 会社の慣習として、福利厚生による弔電へは口頭でのお礼で良いとされている場合(事前に確認できると安心です)
このような場合は、心を込めて口頭でお礼を伝えれば、必ずしもお礼状を送なくても理解されることが多いでしょう。
大切なのは、形式にこだわりすぎず、相手への感謝の気持ちを誠実に伝えることです。迷った場合は、より丁寧な方法(お礼状も送る)を選ぶか、身近な年長者や詳しい方に相談してみるのも良いでしょう。
弔電に対して、口頭とお礼状の両方でお礼するのは、やりすぎでしょうか?
いいえ、むしろ両方行うことで相手への感謝の気持ちがより丁寧に伝わります。相手が目上の方や、今後もお付き合いがある方であれば特に効果的です。
弔電のお礼を口頭で伝える具体的な言い方【例文付き】

いざ口頭でお礼を伝えようとしても、「どんな言葉を選べばいいのだろう」「『ありがとうございました』だけでは足りない気がする…」と悩んでしまうかもしれません。ここでは、失礼なく感謝の気持ちを伝えるための基本的な構成と、具体的な例文をご紹介します。
弔電のお礼、口頭でなんて言う?感謝を伝える基本構成
口頭でお礼を伝える際は、以下の要素を盛り込むと、丁寧で心のこもった感謝の気持ちが伝わりやすくなります。
- 弔電へのお礼: まず、弔電をいただいたことへの感謝を明確に伝えます。
- 例:「このたびは、ご丁寧な弔電をいただき、誠にありがとうございました。」
- 葬儀の無事終了報告: おかげさまで葬儀を無事に終えられたことを報告します。
- 例:「おかげさまで、滞りなく葬儀を終えることができました。」
- 故人が生前お世話になったことへの感謝(任意): 相手と故人の関係性に応じて、生前のご厚誼への感謝を述べます。
- 例:「生前は〇〇(故人名)が大変お世話になり、故人に代わりましてお礼申し上げます。」
- 今後の変わらぬお付き合いのお願い(任意): 今後も良好な関係を続けたい旨を伝えます。特に会社関係者などに対して添えると良いでしょう。
- 例:「今後とも変わらぬご指導(お付き合い)のほど、よろしくお願いいたします。」
これらの要素を基本に、心を込めて、誠実な態度で伝えることが何よりも大切です。早口になったり、目を合わせなかったりすると、感謝の気持ちが伝わりにくくなってしまいます。落ち着いて、相手の目を見て話すように心がけましょう。
弔電のお礼「ありがとうございました」を含む丁寧な例文集
基本的な構成を踏まえ、具体的な状況で使える例文をいくつかご紹介します。相手や状況に合わせて調整して使ってみてください。
【基本的な例文】
「このたびは、(故人名)の葬儀に際し、ご丁寧な弔電をいただき、誠にありがとうございました。おかげさまで、滞りなく葬儀を終えることができました。生前賜りましたご厚情に、故人に代わりまして厚く御礼申し上げます。」
【少し簡潔に伝える場合】
「先日は、心のこもった弔電をいただき、本当にありがとうございました。おかげさまで、無事に(故人名)を見送ることができました。励ましのお言葉、大変ありがたく存じます。」
【相手の心遣いに特に感謝を伝えたい場合】
「このたびは、ご多忙中にも関わらず、〇〇(故人名)のためにお心のこもった弔電を賜り、誠にありがとうございました。温かいお心遣いに、家族一同、大変慰められました。おかげさまで、葬儀も無事に終えることができました。」
【「ありがとうございました」に添える言葉の例】
- 「ご丁寧な弔電をいただき、誠にありがとうございました。」
- 「温かいお悔やみのお言葉、本当にありがとうございました。」
- 「お心遣い、深く感謝申し上げます。ありがとうございました。」
このように、「ありがとうございました」の前後に具体的な言葉を添えることで、より丁寧で心のこもった印象になります。
弔電のお礼の口頭での言い方:状況別のフレーズ調整
お礼を伝える相手や状況によって、言葉遣いや丁寧さの度合いを調整することも大切です。
- 目上の方(上司など)へ: より丁寧な言葉遣いを心がけましょう。謙譲語(申し上げる、拝受するなど)や尊敬語を適切に使うと良いでしょう。
> 例:「この度は、〇〇(故人名)の葬儀に際し、ご鄭重なる弔電を賜り、誠にありがとうございました。部長には日頃より大変お世話になっております上に、このようなお心遣いをいただき、恐縮に存じます。」 - 親しい同僚や友人へ: 基本的なマナーは守りつつ、少し柔らかい表現を使っても良いでしょう。
> 例:「〇〇さん、先日は弔電ありがとう。すごく励みになったよ。おかげさまで、無事に父を見送ることができました。」 - 近所の方へ: 簡潔に、かつ丁寧に伝えることを意識しましょう。
> 例:「〇〇さん、先日はご丁寧な弔電をありがとうございました。おかげさまで、無事に葬儀を終えることができました。」
状況としては、相手が忙しくなさそうな時を見計らうのが基本です。また、あまり長々と話し込むのは避け、感謝の気持ちを簡潔に伝えるようにしましょう。もし、後日ゆっくり話せる機会があれば、「その節はありがとうございました。おかげさまで少し落ち着きました」など、改めて触れるのも良いでしょう。
“電話だけでは略式すぎる?”と悩む方もいますが、状況によっては迅速に感謝を伝える手段として有効です。
電話で弔電のお礼を伝える場合の言い方とマナー
電話でお礼を伝える場合は、直接会う場合とは異なる配慮が必要です。
- タイミング: 葬儀の翌日など、なるべく早いタイミングでかけるのがマナーとされています。ただし、相手の都合が良い時間帯(早朝・深夜・食事時を避ける)を選びましょう。
- 要件は手短に: 電話は相手の時間を拘束するため、弔電への感謝と葬儀の無事終了の報告を主目的とし、手短に済ませるように心がけます。長話は避けましょう。
- 略式であることのお詫び: 電話でのお礼は略式にあたるため、「本来であれば直接お伺いすべきところ、お電話にて失礼いたします」といった一言を添えると、より丁寧な印象になります。
【電話での例文】
「〇〇(相手の名前)様、△△(自分の名前)でございます。先日は、父〇〇(故人名)の葬儀に際しまして、ご丁重なる弔電を賜り、誠にありがとうございました。おかげさまで、葬儀も昨日、滞りなく執り行うことができました。本来であれば直接お伺いしてお礼を申し上げるべきところですが、取り急ぎお電話にて失礼いたしました。生前賜りましたご厚情に、故人に代わりまして厚く御礼申し上げます。」
電話口では、相手の声のトーンにも気を配り、落ち着いた声で話すようにしましょう。
会社関係者への弔電のお礼:口頭での伝え方と注意点

会社の上司や同僚、取引先などから弔電をいただいた場合のお礼は、今後の仕事上の関係性を良好に保つためにも、特に丁寧に行いたいものです。ここでは、会社関係者へのお礼を口頭で伝える際のマナーや注意点を解説します。
会社からの弔電へのお礼は口頭が基本?判断基準は?
会社関係者へのお礼は、忌引き休暇明けの出社時に、上司や部署の同僚へ直接口頭で伝えるのが基本とされています。その際には、弔電へのお礼だけでなく、急な休みに対するお詫びや、不在中の業務フォローへの感謝の気持ちも合わせて伝えましょう。(出典: 電報ならVERY CARD)
ただし、以下のような場合は、口頭でのお礼に加えて、または口頭でのお礼の代わりに、別途対応が必要になることがあります。
- 会社全体や社長名義でいただいた場合: 直接会ってお礼を伝える機会がない社長や役員に対しては、別途お礼状を送るのがより丁寧です。
- 会社の福利厚生として手配された弔電の場合: 会社の慣習にもよりますが、経費で手配された福利厚生の一環であれば、手配を担当した部署(総務部など)や直属の上司への口頭でのお礼のみで良いとされるケースもあります。事前に社内の慣習を確認しておくと安心です。
- 取引先からいただいた場合: 基本的にはお礼状を送るのが望ましいでしょう。担当者の方に直接会う機会があれば、その際に口頭でもお礼を述べるとより丁寧です。
判断に迷う場合は、上司や先輩に相談してみるのが良いでしょう。
忌引き明け出社時:会社での弔電のお礼の言葉(例文)
忌引き休暇明けに出社した際は、まず上司や同僚へ挨拶をしましょう。その際に、以下のような言葉でお礼と復帰の挨拶を伝えます。
「皆様、おはようございます。このたびは、父〇〇(故人名)の葬儀に際し、ご丁寧な弔電をいただき、誠にありがとうございました。また、急なお休みをいただき、皆様には大変ご迷惑とご心配をおかけいたしました。おかげさまで、無事に葬儀を終えることができました。不在の間、業務をサポートしていただき、心より感謝申し上げます。本日からまた気持ちを新たに努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。」
朝礼などの場で全体に挨拶する場合は上記のような形が良いでしょう。個別に上司や特にサポートしてくれた同僚へは、改めて「〇〇部長、先日は弔電をいただきありがとうございました。また、不在の間、ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。〇〇部長にご担当いただいた件、後ほど状況を伺ってもよろしいでしょうか」のように、個別の感謝と業務への復帰姿勢を示すと、よりスムーズです。
上司や社長への弔電のお礼:口頭とメールの使い分け
上司や社長など、目上の方への弔電のお礼は、可能な限り直接口頭で伝えるか、正式なお礼状を送るのが最も望ましい方法です。
しかし、社長が遠方にいる、あるいは多忙で直接会う機会がなかなかない、といった状況も考えられます。そのような場合に、やむを得ずメールでお礼を伝える際には、細心の注意が必要です。
基本的には、まず口頭で伝えられる機会を探し、それが難しい場合に限り、丁寧なメールを送るという順番で考えましょう。メールを送る場合でも、後日会う機会があれば、改めて口頭でお礼を伝えるのがマナーです。
会社への弔電のお礼メールは失礼?送る際の注意点
前述の通り、弔電のお礼をメールで行うことは略式とみなされ、相手によっては失礼だと受け取られる可能性も否定できません。特に弔事に関する連絡は、伝統的なマナーを重んじる傾向があります。
ただし、以下のような状況では、メールでのお礼も許容される場合があります。
- 普段からメールでのコミュニケーションが主な相手
- 直接会う機会がすぐにはない遠方の支社の同僚など
- 社内の慣習としてメールでの連絡がある程度認められている場合
もしメールでお礼を送る場合は、必ず以下の点に注意してください。
- 件名: 「【御礼】弔電のお礼(自分の氏名)」のように、一目で内容と差出人が分かるようにします。
- 宛名: 会社名、部署名、役職、氏名を正確に記載します。
- 本文:
- 弔電への感謝を丁寧に述べます。
- 葬儀が無事に終わったことを報告します。
- 「本来であれば直接お礼を申し上げるべきところ、メールにて失礼いたします」といった、略儀でのお礼に対するお詫びの言葉を必ず添えます。
- (必要であれば)今後の仕事への意欲なども簡潔に記します。
- 言葉遣い: 尊敬語・謙譲語を正しく用い、丁寧な文章を心がけます。
- 送信タイミング: 業務時間内に送るのが基本です。
あくまでメールは補助的な手段と考え、可能な限り直接伝える努力を優先しましょう。
会社から弔電へのお礼にLINEは使える? 基本的な考え方
LINEやその他のSNS、チャットツールを使った弔電のお礼は、ビジネスマナーとしても、弔事のマナーとしても、基本的に避けるべきです。
メール以上にカジュアルな印象を与え、相手に「礼儀を知らない」「不謹慎だ」といった不快感を与えかねません。たとえ普段からLINEでやり取りしている親しい同僚であっても、弔電という改まった弔意に対しては、口頭、手紙(お礼状)、または状況に応じた丁寧なメールでお礼を伝えるのが適切な対応です。
プライベートな連絡ツールと、フォーマルな場でのコミュニケーションは、明確に区別するようにしましょう。
弔電のお礼に関するよくある質問とまとめ
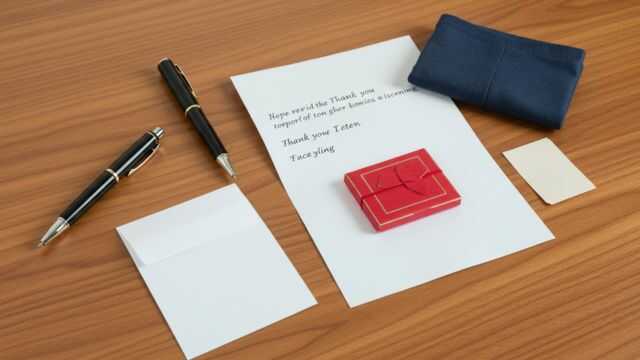
ここまで、弔電のお礼を口頭で伝える際のマナーや例文、会社での対応について解説してきました。最後に、弔電のお礼に関して多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。
弔電へのお礼は口頭だけでなく、お礼状も送るべきですか?
口頭で伝えた場合でも、お礼状を送るのが最も丁寧な対応です。特に目上の方や、今後もお付き合いを続けたい相手には、書面でも感謝を表すことが望ましいでしょう。
弔電のお礼を伝えるときに避けるべき言葉はありますか?
はい、「重ね重ね」「再び」「死ぬ」などの忌み言葉は避けましょう。故人を偲ぶ場面では、不吉な言葉を使わず、丁寧で穏やかな表現を心がけるのがマナーです。
葬式で電報(弔電)をもらったらお礼は必須?
はい、弔電をいただいたら、必ずお礼をするのがマナーです。弔電は、故人を偲び、遺族を励ますために送られるものです。その温かい心遣いに対して、感謝の気持ちを伝えることは、人としての礼儀と言えるでしょう。
お礼の方法(直接訪問、電話、お礼状、口頭)は、相手との関係性や状況に応じて適切なものを選びますが、いずれかの形でお礼の気持ちを伝えることが大切です。
弔電のみいただいた場合、お返しの品物は必要?
はい、弔電をいただいたら、必ずお礼をするのがマナーです。弔電は、故人を偲び、遺族を励ますために送られるものです。その温かい心遣いに対して、感謝の気持ちを伝えることは、人としての礼儀と言えるでしょう。
お礼の方法(直接訪問、電話、お礼状、口頭)は、相手との関係性や状況に応じて適切なものを選びますが、いずれかの形でお礼の気持ちを伝えることが大切です。
お礼を伝える際に避けたい言葉や態度は?(忌み言葉など)
弔電のお礼を伝える際には、忌み言葉(いみことば)の使用を避けるのがマナーです。(出典: e-denpo, https://www.e-denpo.net/弔電で避けるべき「忌み言葉」とは?宗教別の文例も/) 忌み言葉とは、不幸が重なることや不吉なことを連想させる言葉のことです。
【忌み言葉の例】
- 不幸の重なりを連想させる言葉(重ね言葉): 重ね重ね、たびたび、ますます、いよいよ、次々 など
- 不幸が続くことを連想させる言葉: 再び、引き続き、追って など
- 不吉な言葉: 消える、浮かばれない、四(死)、九(苦) など
- 生死を直接的に表現する言葉: 死ぬ、急死、生きていたころ など (「ご逝去」「ご生前」などに言い換える)
これらの言葉は無意識に使ってしまうこともあるため、注意が必要です。
また、言葉遣いだけでなく、態度も重要です。感謝の気持ちを伝える際は、誠実で落ち着いた態度を心がけましょう。早口になったり、目を合わせなかったり、逆に必要以上に明るく振る舞ったりするのは避け、故人を悼む気持ちと、弔意への感謝が伝わるように努めましょ
誰かの思いやりに『ありがとう』と返すことが、遺族としての一つの務めなのだと、私は感じています。
まとめ:弔電へのお礼は心を込めて失礼なく伝えよう

今回は、弔電のお礼を口頭で伝える際のマナー、タイミング、具体的な言い方や例文、会社での対応について詳しく解説しました。
弔電のお礼で最も大切なことは、形式やマナーを守ること以上に、いただいた弔意に対して心からの感謝の気持ちを誠実に伝えることです。
葬儀後の慌ただしい時期ではありますが、少し落ち着いたら、相手への配慮を忘れずに、適切な方法でお礼を伝えましょう。口頭でお礼を述べる際は、タイミングを見計らい、丁寧な言葉遣いを心がけ、誠実な態度で臨むことが大切です。
この記事でご紹介した内容が、あなたの「弔電のお礼をどう伝えればいいのだろう」という不安を解消し、自信を持って感謝の気持ちを伝えるための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。
まとめ
- 弔電のお礼は葬儀後1週間以内が目安である
- お礼の方法は直接訪問・お礼状・電話・口頭がある
- 口頭でお礼を伝えるタイミングは相手の状況に配慮する
- 口頭でのお礼に加えお礼状を送るのが最も丁寧である
- お礼の言葉は「感謝」と「葬儀終了報告」を基本とする
- 状況に応じた丁寧な例文を参考に表現を調整する
- 電話で伝える際は略式である旨のお詫びを添える
- 会社関係者へは忌引き明けに口頭で伝えるのが基本
- メールでのお礼は略式と理解し細心の注意を払う
- LINEなどSNSでのお礼は基本的に避けるべき
- 弔電のみならお返しの品物は不要である
- 忌み言葉を使わず誠実な態度で感謝を伝える

