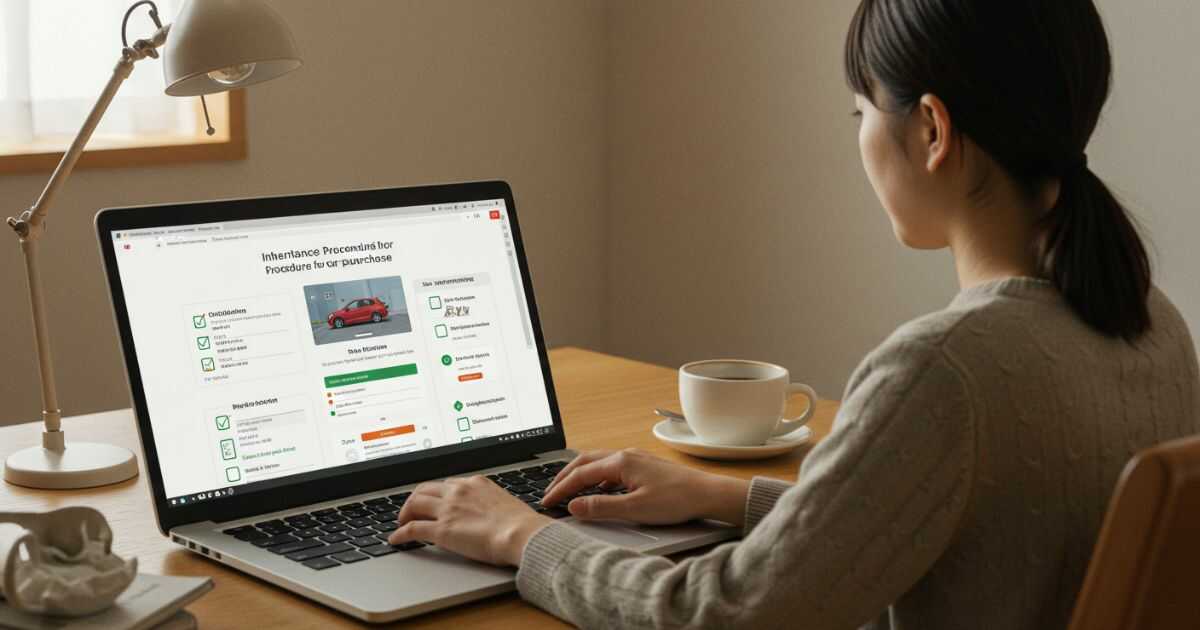まとまった資金が手元に入るのは心強い反面、それがご家族が残してくれた大切な遺産となると、「どう使うのが一番良いのだろう…」「手続きとか税金とか、なんだか難しそう…」と、色々な想いや疑問が湧いてくることと思います。
特に、長年連れ添った愛車の買い替え時期が近づいていたり、ライフスタイルが変わるタイミングだったりすると、「遺産で車を買う」という選択は、とても魅力的に感じられるでしょう。
しかし、ちょっと待ってください。「遺産で車を買う」場合、普段の車の売買とは違う、特有の手手続きや税金のルールがあるんです。これを事前に知っておかないと、思わぬ手間がかかったり、後で「しまった!」ということになりかねません。
この記事では、そんなあなたの疑問や不安を解消するために、「遺産で車を買う」ときに必ず知っておきたいポイントを客観的な情報に基づいて、分かりやすく解説します。相続手続きの基本から、気になる税金、後悔しないための車の選び方まで、順を追って丁寧にご説明しますね。
この記事を最後まで読めば、遺産という大切な資金をどう活かすべきか、具体的な道筋が見えてくるはず。安心して、あなたにとって最良のカーライフへの一歩を踏み出しましょう!
- 遺産での車取得には特有の相続手続きが必須。
- 状況により相続税や贈与税がかかるため確認が必要。
- 維持費を含めた予算とライフプランに合う車選びが重要。
- 遺産特有の注意点を理解し計画的に進めることが大切。
遺産で車を買う前に知るべき手続きと税金

親が亡くなった後、車はどうなるの?
このテーマ、実は相談件数がとても多いんです。『車は相続の対象になるの?』と不安に思われる方は本当に多いですね。
親御さんなど、これまで車を使っていた方が亡くなられた場合、まず気になるのは「この車、これからどうなるんだろう?」ということですよね。
結論からお伝えすると、その車は法的に「相続財産」の一部として扱われます。これは、ご自宅や預貯金などと同じ、いわば故人の財産リストの一つになる、ということです。
なぜかと言うと、日本の法律では、亡くなった方(法律用語で「被相続人」といいます)が持っていた財産に関する権利や義務は、基本的に相続人(配偶者やお子さんなど)に引き継がれると決まっているからです。ですから、車も当然、相続の対象になるわけですね。
具体的には、車の所有者が亡くなったその瞬間から、車は相続人全員の「共有財産」という状態になります。「共有」というと少し分かりにくいかもしれませんが、相続人みんなで一時的に共同所有しているイメージです。
そのため、たとえ「私がこの車を引き継いで乗りたい」とか、「もう誰も使わないから早く売りたい」と思っていても、相続人の誰か一人の判断で、勝手に名義変更したり、売却や廃車の手続きを進めたりすることはできません。
まずやるべきことは、相続人全員で「遺産分割協議」という話し合いを持つことです。この話し合いで、「誰が車を相続するのか」「売却して現金で分けるのか」などを決めます。もし、故人が遺言書で車の相続人を指定していれば、原則はその遺言の内容に従うことになります。
この相続手続き、特に車の名義変更をしないまま放置してしまうと、後々面倒なことになりかねません。
- 法律上の義務: 道路運送車両法では、所有者が変わってから15日以内に名義変更(移転登録)をするよう定められています。これに違反すると、最大で50万円以下の罰金が科される可能性も。
- 売却・廃車ができない: 故人名義のままでは、車を売ったり、廃車にしたりする手続きが一切できません。
- 保険の問題: 万が一、故人名義の車で事故を起こしてしまった場合、任意保険が使えず、十分な補償を受けられないリスクがあります。
このように、親御さんが亡くなって車が残された場合は、面倒に感じても、できるだけ早く相続手続きを進めることがとても大切なのです。
まず確認!車の所有者とローン残高
ローン会社に問い合わせる時って、何を聞けばいいんでしょうか?
まずはローンの残高と、所有権留保が解除できるかどうかを確認するのが第一です。その際に必要書類や手続きの流れも聞いておくと安心ですよ。
相続手続きを進める上で、絶対に最初に確認しなければならない、とても重要なポイントがあります。それは、「亡くなった親御さんが、本当にその車の法的な『所有者』だったのか?」ということです。
「え?親が乗っていたんだから、所有者に決まってるじゃないか」と思われるかもしれません。しかし、必ずしもそうとは限らないのです。この確認は、お手元にある(または車内に保管されている)車検証(自動車検査証)を見ればすぐに分かります。
車検証の中ほどにある「所有者の氏名又は名称」という欄をチェックしてみてください。ここに書かれているのが、法律上の正式な所有者です。この所有者名義によって、今後の手続きがガラッと変わってきます。
ケース1:所有者欄が「亡くなった親御さんご本人」の名義の場合
この場合はシンプルです。車は間違いなく相続財産ですので、前の項目で説明した通り、遺産分割協議を経て、相続手続き(名義変更など)を進めていくことになります。
ケース2:所有者欄が「ローン会社」や「ディーラー(自動車販売店)」の名義の場合
こちらが注意の必要なケースです。車をローンで購入した場合、完済するまでの間、所有権をローン会社やディーラーに残しておく契約(これを「所有権留保」といいます)になっていることがよくあります。
この場合、法的な所有権はローン会社などにあるため、亡くなった親御さんは「使用者」であっても「所有者」ではありません。したがって、厳密には、この状態の車をそのまま相続財産として分割したり、勝手に売却したりはできないのです。
では、どうすれば良いのでしょうか?
まずは、車検証に記載されている所有者(ローン会社やディーラー)に連絡を取り、ローンの残高がいくらあるかを確認しましょう。
- もしローンが既に完済されていたら? 所有権留保の解除手続きを依頼します。手続きが完了すれば、車の所有者名義を(一旦、亡くなった親御さん名義などに)変更してもらえるので、その後、通常の相続手続きが可能になります。必要書類はローン会社に確認しましょう。
- もしローンがまだ残っていたら? 相続人がその車を引き継ぎたい場合、選択肢は主に2つです。
- 残りのローンを一括で支払う。
- 相続人が新たにローンを組み直す(または契約を引き継ぐ)。 この場合、ローン会社による審査が必要になることが一般的です。 もし、車が不要であれば、ローン会社に車を引き渡して清算する方法もあります。ただし、車の査定額(売却額)がローン残高に満たない場合は、差額分を相続人が支払う必要が出てくる可能性があります。例えば、ローン残高が50万円で、車の査定額が30万円だった場合、差額の20万円を支払う、といった具合です。
このように、車検証で「所有者」を確認し、ローン残高の有無を把握することは、相続手続きの出発点として非常に重要です。ここを間違えると、後々手続きが滞ってしまう可能性があるので、しっかりと確認してくださいね。
車相続に必要な「車遺産分割協議書」
ここからが実務的な山場です。『協議書』という言葉に身構える方も多いですが、落ち着いて順を追えば大丈夫ですよ。
さて、車の所有者名義やローンの状況が確認できたら、次のステップは相続人同士の話し合いです。遺言書で車の相続人が明確に指定されていない限り、「誰がこの車を相続するのか」を相続人全員で決める必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」と呼びます。
そして、この遺産分割協議で決まった内容を、法的に有効な形で記録・証明するために作成するのが「遺産分割協議書」という書類です。
なぜこの書類がそんなに重要なのでしょうか? それは、車の名義変更(移転登録)手続きを行う運輸支局(陸運局とも呼ばれます)で、原則としてこの遺産分割協議書の提出が求められるからです。「相続人全員が納得して、この人が車を相続することに合意しましたよ」という客観的な証拠になるわけですね。
遺産分割協議書には、特に法律で定められた厳密な書式はありません。しかし、手続きをスムーズに進め、後々のトラブルを防ぐためには、以下の点を正確に記載することが重要です。
- 誰の遺産分割協議か(被相続人の特定): 亡くなった方の氏名、最後の住所、死亡年月日などを記載します。
- 誰が協議に参加したか(相続人の特定): 相続人全員の氏名と住所を記載します。
- 協議が成立した日付
- 分割内容: どの財産を誰が相続するかを具体的に書きます。車の場合は、車検証に記載されている通りに、登録番号(ナンバープレートの番号)と車台番号を正確に記載し、「相続人〇〇(氏名)がこれを相続する」といった形で明記します。
- 後日発見された遺産の扱い(任意): 記載しておくと、万が一新たな遺産が見つかった場合の対応がスムーズになります。
- 相続人全員の署名
- 相続人全員の実印での捺印
ここで特に注意が必要なのは、必ず相続人全員が実印で捺印することです。認印では認められません。そして、その実印が本人のものであることを証明するために、発行から3ヶ月以内の印鑑証明書を、相続人全員分、遺産分割協議書に添付する必要があります。
もし相続人の中に未成年者がいる場合は、その未成年者の代わりに「特別代理人」を家庭裁判所で選任し、その特別代理人が署名・捺印することになります。
遺産分割協議書の作成は、少し手間がかかる作業かもしれません。しかし、これは車だけでなく、不動産や預貯金など他の遺産を相続する際にも基本となる重要な書類です。もしご自身での作成に不安がある場合や、相続人間で意見がまとまりにくい場合は、行政書士や弁護士といった専門家に相談するのも一つの手です。作成代行の費用は、内容にもよりますが、一般的に数万円から十数万円程度が目安と言われています。専門家に依頼すれば、法的に不備のない書類を作成してもらえ、手続きもスムーズに進むでしょう。
「自動車相続100万円以下」の簡易手続き
前の項目でご説明した車の相続手続きには、原則として相続人全員の実印と印鑑証明書が付いた「遺産分割協議書」が必要ですが、相続人全員から書類を集めるのは、特に遠方に住んでいる方がいる場合など、なかなか大変ですよね。
そこで朗報です! 実は、相続する車の価値(査定額)が100万円以下の場合に限っては、手続きをぐっとシンプルにできる特例(簡易手続き)が用意されています。この手続きでは、「遺産分割協議書」の代わりに「遺産分割協議成立申立書」という書類を使います。
この簡易手続きがなぜ認められているかというと、比較的高額ではない車の相続についてまで、相続人全員の厳格な書類を求めるのは、手続きの負担が大きすぎるだろう、という配慮からです。よりスムーズに、早く名義変更を済ませられるようにという目的があるのですね。
では、具体的に通常の遺産分割協議書を使った手続きとどう違うのでしょうか? 最大の違いは、必要となる人の範囲と書類です。
- 通常の手続き(遺産分割協議書):
- 相続人全員の署名・実印での捺印が必要。
- 相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)が必要。
- 簡易手続き(遺産分割協議成立申立書):
- 車を相続する代表者1名の署名・実印での捺印だけでOK。
- 車を相続する代表者1名の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)だけでOK。
つまり、この簡易手続きなら、他の相続人の方に実印を押してもらったり、印鑑証明書を取り寄せてもらったりする手間が一切不要になるんです! これは大きなメリットですよね。
ただし、この便利な簡易手続きを利用するには、絶対に満たさなければならない条件があります。それは、「相続する車の査定額が100万円以下であること」を客観的に証明する書類(査定証など)を、遺産分割協議成立申立書に添付することです。この査定証の取得方法については、次の項目で詳しく解説しますね。
この簡易手続きは非常に便利ですが、いくつか注意点もあります。
- あくまで車の相続手続きが簡略化されるだけで、他の遺産(不動産や預貯金など)の分割協議や手続きが不要になるわけではありません。
- 相続人間で、車の評価額や誰が相続するかについて、もめ事がないことが大前提です。「本当に100万円以下なの?」「私が相続したかったのに」といった意見の対立がある場合は、この方法は使えません。
もし、車の価値が100万円を超えるか微妙なラインの場合や、少しでも相続人間で意見が割れる可能性があるなら、後々のトラブルを避けるためにも、通常通り、正式な遺産分割協議書を作成する方が賢明かもしれません。ご自身の状況をよく考えて、最適な方法を選びましょう。
私のおすすめは、少しでも迷ったら“正式な協議書を作る”方向で動くこと。その方が後々安心です。
100万円以下の査定証はどこで取る?
前の項目でご説明した「自動車相続100万円以下」の簡易手続き。これを利用するために不可欠なのが、「車の査定額が100万円以下であること」を証明する査定証です。では、この信頼できる査定証は、具体的にどこで手に入れればよいのでしょうか?
結論から言うと、最も確実で推奨されるのは、第三者機関である「一般財団法人 日本自動車査定協会(JAAI)」に査定を依頼し、正式な査定証を発行してもらう方法です。
JAAIは、中古車の適正な査定基準を定めたり、査定を行う査定士の資格制度を運営したりしている、いわば中古車査定のプロ集団であり、公的な性格を持つ団体です。そのため、JAAIが発行する査定証は、運輸支局(陸運局)での手続きにおいて、その証明力が高く評価され、広く認められています。
JAAIに査定を依頼する流れは、おおむね以下の通りです。
- 申し込み: まず、お近くのJAAIの支所に電話などで連絡を取り、査定を申し込みます。「相続手続き(遺産分割協議成立申立書添付用)のための査定をお願いしたい」と伝えるとスムーズでしょう。
- 査定の実施: 車をJAAIの支所に持ち込んで査定してもらうか、査定士に指定の場所まで来てもらう出張査定(別途、出張費用がかかる場合があります)かを選べる場合があります。
- 必要書類の確認: 車検証や自賠責保険証明書の提示を求められることがあるので、事前に確認しておくと良いでしょう。
- 査定と査定証の発行: 専門の査定士が、車種、年式、走行距離、車の状態(傷、へこみ、修復歴の有無など)、装備などを細かくチェックし、JAAI独自の基準に基づいて評価額を算出します。査定後、正式な査定証が発行されます。
- 費用の支払い: 査定費用は、車種や地域、出張の有無などによって異なりますが、一般的には1万円~2万円程度が目安です。これには査定証の発行手数料も含まれていることが多いです。正確な料金は、依頼するJAAI支所に必ず確認してください。
もちろん、JAAI以外にも、お付き合いのあるディーラーや、街の中古車買取専門店に査定を依頼し、査定額が記載された書類を発行してもらう、という方法も考えられます。無料で査定してくれる業者も多いでしょう。
ただし、注意点として、これらの業者の査定は、あくまで「買取」を前提とした価格提示であったり、簡易的な評価であったりする可能性もあります。運輸支局での手続きで確実に受理されるためには、やはりJAAIのような客観的で信頼性の高い第三者機関の査定証を取得しておくのが、最も安心できる方法と言えるでしょう。
相続開始(亡くなった日)から時間が経つと車の価値も変動しますので、簡易手続きの利用を検討している場合は、なるべく早めに査定を受けることをおすすめします。
「遺産の車には税金はかかりますか?」を解説
遺産として車を引き継ぐことになった場合、多くの方が心配されるのが「税金って、かかるの?」という点だと思います。特に相続税については、あまり馴染みがない方も多いかもしれませんね。
結論としては、はい、遺産の車も他の財産と同様に評価され、相続税の課税対象となる可能性があります。
なぜなら、相続税というのは、亡くなった方が残した「すべての財産」の合計額に対してかかる税金だからです。現金や預貯金、不動産、株式などはもちろん、車や貴金属、骨董品なども、金銭的な価値があるものは基本的にすべて相続財産に含まれます。ですから、車もそのリストに入る、というわけですね。
「えっ、じゃあ必ず税金を払わないといけないの?」と不安になるかもしれませんが、そういうわけではありません。相続税には「基礎控除」という、いわば“非課税の枠”が設けられています。
遺産の総額(借金などマイナスの財産も考慮します)が、この基礎控除の金額よりも少なければ、相続税は一切かかりません。そして、相続税がかからない場合は、税務署への申告も不要です。
では、その基礎控除額はいくらなのでしょうか? これは法律で決まっていて、以下の計算式で求められます。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
※法定相続人とは、法律で定められた相続人のことです。通常は配偶者や子供などが該当します。
例えば、相続人が奥様とお子さん2人の合計3人だった場合を考えてみましょう。
基礎控除額は、3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円 となります。
この場合、車の評価額を含むすべての遺産の合計額が4,800万円以下であれば、相続税の心配はない、ということになりますね。
ここで重要になるのが、「車の評価額をいくらで計算するか」です。相続税の計算に使う車の評価額は、新車で買ったときの値段ではありません。そうではなく、相続が開始した時点(つまり、亡くなった日)での「時価」で評価します。
この「時価」を調べる方法としては、一般的に以下のいずれかが用いられます。
- 中古車買取業者やJAAIなどによる査定額
- インターネット等で調べた同程度の車の買取相場
- 相続発生直後に売却した場合の、その売却価格
注意点として、車の評価額そのものはそれほど高くなくても(例えば100万円とか)、他に高額な不動産や預貯金がたくさんある場合は、遺産の総額が基礎控除額を超えてしまい、相続税が発生する可能性があります。
逆に、もし亡くなった方が車のローンをまだ支払っている途中だった場合は、そのローン残高は「マイナスの財産(債務)」として、遺産の総額から差し引くことができます。
相続税の計算や申告(申告が必要な場合の期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です)は、財産の種類が多かったり、評価が複雑だったりすると、なかなか難しいものです。もし遺産の総額が基礎控除額を超えそうな場合や、ご自身での判断に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することを強くおすすめします。相続税に詳しい税理士なら、適切な財産評価や申告手続きをサポートしてくれますよ。相談費用はかかりますが、申告漏れによるペナルティなどを考えれば、結果的に安心につながるはずです。
「親に車を買ってもらうと贈与税はかかりますか?」を解説
ここまでは主に「亡くなった親の車を相続する」ケースについてお話ししてきましたが、少し状況を変えて考えてみましょう。例えば、「相続した遺産(現金)を使って、親が子供に車を買ってあげる」とか、「親が自分の貯金から、子供のために車を買ってあげる」といった場合です。
このようなケースで気をつけたいのが「贈与税」です。「人から財産をもらうと税金がかかる」という話を聞いたことがあるかもしれませんが、親子間であっても、一定の金額を超えると贈与税の対象になる可能性があるのです。
まず、今回の記事のメインテーマである「ご自身が相続した遺産(現金)で、ご自身の車を買う」場合。これは、贈与税の心配は全くありません。なぜなら、あくまでご自身の財産を使う行為であり、誰かから財産を「もらった」わけではないからです。ここははっきり区別しておきましょう。
では、どのような場合に贈与税がかかる可能性があるのでしょうか?
それは、「年間(その年の1月1日から12月31日まで)に、合計110万円を超える財産を、個人からもらった」場合です。この110万円という金額は「暦年贈与の基礎控除額」と呼ばれ、いわば贈与税がかからない非課税の枠です。逆に言えば、この枠を超えた部分に対して贈与税が課税される仕組みになっています。
車に関して、具体的に贈与税がかかる可能性があるのは、主に次のようなケースです。
- 親が、110万円を超える価格の車をディーラーなどで購入し、それを子供名義で登録してプレゼントした場合: この場合、車の購入代金そのものが贈与額とみなされます。例えば、親が子供のために300万円の新車を買ってあげたとすると、基礎控除110万円を引いた190万円(300万円 - 110万円)が課税対象となります。贈与税を支払うのは、車をもらった子供自身です。
- 親が、子供の車の購入資金として、年間で110万円を超える現金を援助した場合: 援助した現金の合計額が贈与額となります。
- 親が使っていた中古車(査定額が110万円を超えるもの)を、子供に無償で(タダで)譲った場合: この場合は、その中古車の査定額(時価)が贈与額とみなされます。もし子供が親にいくらか代金を支払って譲り受けた場合は、「査定額 - 支払った代金」が贈与額となります。
贈与税の税率は、もらった金額(基礎控除後の課税価格)によって10%から最大55%まで段階的に上がっていきます。また、親や祖父母から18歳以上(※)の子や孫への贈与の場合は、それ以外の贈与(兄弟間など)よりも税率が少し低く設定されています(特例税率)。
(※令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上)
ただし、ここにも例外があります。親が子供に対して、生活していく上で通常必要なお金(生活費や教育費など)を援助する場合は、贈与税の対象外となります。例えば、地方に住む子供が通学や通勤にどうしても車が必要で、そのために親が一般的な価格の車を買ってあげるようなケースは、扶養義務の範囲内として非課税になる可能性もあります。しかし、これが趣味のための高級車だったり、公共交通機関が便利な都市部での利用だったりすると、非課税とは認められないことが多いでしょう。
「親に車を買ってもらう」という状況は、贈与税がかかるかどうかの判断が少し難しい場合があります。年間110万円という基礎控除額を念頭に置きつつ、もし高額な車や資金援助を考えている場合は、事前に税務署や税理士に相談するのが最も確実で安心です。
後悔しない!遺産で車を買う際の賢い選択

さて、相続に関する手続きや税金の基本的な知識が身についたところで、いよいよ「どの車を選ぶか」という、ワクワクするけれど悩ましいステップですね!
車選び、何を基準にすれば後悔しませんか?
大切なのは、“必要な機能”と“無理のない予算”を基準にすること。長く使えるかどうかが鍵ですよ。
遺産という、ある意味で特別な資金が手元にあると、「せっかくだから、ちょっと良いグレードの車にしようかな」「昔から憧れていたあの輸入車も夢じゃないかも…」なんて、ついつい気持ちが大きくなってしまうこともあるかもしれません。
もちろん、故人を偲び、残してくれた遺産をご自身の人生の楽しみに使うことは、決して悪いことではありません。むしろ、故人も喜んでくれるかもしれませんよね。
しかし、「遺産で車を買う」という状況だからこそ、一呼吸置いて、冷静に、そして長期的な視点で考えることが、後で「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないために、とても大切になってきます。
このセクションでは、具体的な予算の考え方から、あなたの今の、そしてこれからのライフプランに本当にフィットする車種選びのヒント、さらには「遺産だから」と浮かれずに賢く判断するための注意点、相続した車をどう活用するかまで、後悔しないための「賢い選択」のポイントを詳しく掘り下げていきます。ここをしっかり読んで、あなたにとって本当に価値のある、長く付き合える最高の一台を見つけるお手伝いができれば嬉しいです。
「遺産で何買う?」後悔しない車の選び方
「遺産で車を買う」――それは、単なる買い物以上の意味を持つかもしれません。故人への感謝、そしてこれからの自分の人生への投資。だからこそ、「買って本当に良かった!」と心から満足できる一台を選びたいものですよね。
では、後悔しないためには、どうやって車を選べばいいのでしょうか?
結論から言うと、「今の、そしてこれからのあなたの生活に本当に必要な車を、無理のない予算内で冷静に見極めること」。これに尽きると言えます。
なぜなら、車は家計における大きな支出であり、購入後も維持費がかかり続けるからです。遺産があるからといって、一時的な感情や憧れだけで選んでしまうと、後々「維持費が思ったより高い…」「家族が増えたら手狭になった」「もっと燃費の良い車にすればよかった…」なんて後悔につながる可能性が高いのです。
そこで、後悔しないための具体的な選び方のステップを考えてみましょう。
- まずは予算!「総額」で考える:最初に、車にかけられる予算の上限を明確にしましょう。遺産の全額を投入するのか、それとも一部にするのか。ここで重要なのは、車両本体価格だけでなく、購入時にかかる諸費用(税金、登録費用など)と、購入後の維持費まで含めた「トータルコスト」で考えることです。維持費には、主に以下のものが含まれます。
- 税金(毎年の自動車税、車検ごとの重量税)
- 保険料(自賠責保険、任意保険)
- 燃料費(ガソリン代、電気代)
- メンテナンス費用(車検、オイル交換、タイヤ交換など)
- 駐車場代(自宅にない場合) 特に、排気量が大きい車、車両価格が高い車、輸入車などは、税金や保険料、部品代が高くなる傾向があります。例えば、年間維持費が数十万円単位で変わってくることも珍しくありません。購入前に、年間の維持費がだいたいいくらかかるのか、ディーラーに聞いたり、ネットで調べたりして、必ずシミュレーションしておきましょう。
- 「誰が、いつ、どう使う?」利用シーンを具体的に:次に、あなたのカーライフを具体的にイメージします。
- 運転するのは主に誰?: ご自身だけ? 奥様も運転しやすい方がいい?
- 乗せる人数は?: 普段は夫婦二人きりでも、独立したお子さんが帰省した時や、ご友人、ご親戚を乗せる機会は?
- 主な用途は?: 毎日の通勤? 近所の買い物? 週末のドライブや旅行? 荷物をたくさん積むことは?
- これから先の生活は?: あと何年くらい運転する予定? 将来、ご両親の介護などで使う可能性は? これらの点を整理することで、必要な車のサイズ(コンパクトカー、セダン、SUV、ミニバンなど)や、重視すべき性能(燃費、安全性、運転のしやすさ、乗り心地、荷室の広さなど)が見えてきます。例えば、長距離運転が多いなら運転支援機能が充実した車、街乗り中心なら小回りの利くコンパクトカー、といった具合です。近年注目されている電気自動車(EV)やハイブリッド車(HV)は燃費が良いですが、車両価格や充電設備なども考慮する必要がありますね。
- 新車? 中古車? それぞれのメリット・デメリット:予算や使い方によって、新車と中古車のどちらが適しているかは変わってきます。
- 新車:
- メリット:最新の安全技術や燃費性能、メーカー保証が付く安心感、色やオプションを自由に選べる満足感。
- デメリット:価格が高い、納車まで時間がかかる場合がある。
- 中古車:
- メリット:新車より価格が安い、同じ予算ならワンランク上の車種やグレードが狙える、納車が比較的早い。
- デメリット:車の状態(修復歴、消耗品の劣化具合など)を見極める必要がある、保証期間が短い場合がある。 最近では、ディーラーが販売する保証付きの認定中古車や、走行距離が極めて少ない「登録(届出)済未使用車」(いわゆる新古車)なども人気があります。選択肢の一つとして検討してみる価値はあるでしょう。
- 新車:
- 情報収集と比較検討、そして試乗!:気になる車種が見つかったら、焦らずじっくり情報収集と比較検討を行いましょう。
- 情報源: メーカー公式サイト、中古車情報サイト(カーセンサー、グーネットなど)、自動車専門サイト(価格.com、レスポンスなど)、個人のレビューブログ、YouTubeの試乗動画など、様々な情報源を活用します。
- 比較: 燃費、安全性能、維持費、リセールバリュー(将来売却するときの価値)などを比較検討します。
- 試乗: カタログやネットの情報だけでは分からない、実際の運転感覚、乗り心地、視界、操作性などを確認するために、試乗は絶対に欠かせません。できれば普段使う道や高速道路なども走ってみると、よりリアルな評価ができます。複数の車種を試乗して比較するのが理想的です。
- ディーラー訪問: 見積もりを取るだけでなく、営業担当者の知識や対応、お店の雰囲気などもチェックしましょう。長く付き合うことになるかもしれませんからね。
遺産での車購入は、特別な機会です。だからこそ、じっくり時間をかけて、情報を集め、比較検討し、実際に試乗して、「これだ!」と思える、あなたにとって本当に価値のある一台を選んでくださいね。
ちょっと待って!「親の遺産で贅沢」の注意点
「親が残してくれた遺産だから、せっかくなら少し贅沢して、良い車に乗りたい!」――そう考える気持ち、とてもよく分かります。予期せぬ収入があれば、普段は手が届かないようなものに心が惹かれるのは自然なことです。
しかし、その気持ちのままに高額な車を選んでしまう前に、少しだけ立ち止まって考えておきたい注意点がいくつかあります。「親の遺産で贅沢」することが、必ずしも悪いわけではありませんが、後々「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないために、冷静に確認しておきましょう。
- 故人(親御さん)の想いを想像してみる:もちろん、遺産の使い道は相続人であるあなたが自由に決められます。法律上は何の問題もありません。ただ、もし親御さんが生前、物を大切にし、堅実な生活を送られていた方だったとしたら、あまりに高額な車を買うことを、天国でどう思われるでしょうか? 「お父さん(お母さん)が汗水流して残してくれたお金だから、無駄遣いはしたくない」…そんな風に考える方もいらっしゃるでしょう。法的なこととは別に、故人の価値観や想いに少しだけ心を寄せてみるのも、大切なことかもしれません。
- 周りの人への配慮も忘れずに:遺産分割協議が円満に終わっていたとしても、他の相続人や親戚の中には、あなたが急に高級車に乗り始めたのを見て、複雑な気持ちになる人がいる可能性もゼロではありません。「自分だけ良い思いをして…」といった感情が、思わぬ人間関係の軋轢を生むことも…。特に、相続の手続きが終わる前に大きな買い物をするのは、誤解を招きやすいので避けた方が賢明です。
- 見落としがちな「維持費」の重さ:これが最も現実的で重要な注意点です。一般的に、車両価格が高い車ほど、維持費も高くなる傾向があります。
- 税金: 自動車税や重量税は、排気量や車両重量に応じて高くなります。例えば、排気量2.5L超~3.0L以下の自動車税は年間50,000円ですが、4.5L超~6.0L以下だと年間87,000円にもなります(2019年10月1日以降新規登録の場合)。
- 保険料: 車両保険の金額が高くなるため、任意保険料も高額になりがちです。
- 燃料費: 排気量が大きい車や車重が重い車は、燃費が悪くなる傾向があります。
- メンテナンス費用: 部品代が高価だったり、特殊なオイルやタイヤが必要だったり、整備に専門知識が必要だったりと、何かとお金がかかることがあります。車検費用も高くなる可能性があります。
- 駐車場代: 高級車の場合、セキュリティのしっかりした駐車場を選びたくなるかもしれませんね。 購入時の予算は何とかなっても、毎月、毎年かかってくる維持費が家計を圧迫してしまう…というのは、よく聞く失敗談です。「憧れの車を買ったはいいけど、維持費が高くて気軽に乗り回せない」なんてことになったら本末転倒ですよね。購入を決める前に、年間の維持費が具体的にどのくらいになるのか、必ずシミュレーションしましょう。ディーラーや保険代理店に相談すれば、概算を教えてくれますよ。
- 本当に今の自分、将来の自分に必要か?:一時的な満足感のために、今の生活や将来設計に見合わない車を選んでしまうと、後で困ることになるかもしれません。「最新の機能だけど、自分には使いこなせないかも」「子供が独立したら、こんなに大きな車は必要ないな」など、長期的な視点で冷静に判断することが大切です。
遺産は、あなたの人生を豊かにする可能性を秘めた、大切な贈り物です。一時の感情に流されず、これらの注意点を踏まえた上で、計画的に、そして感謝の気持ちを持って、最も有意義な使い方を考えてみてくださいね。
実は私も昔、見栄で少し高めの車を買って後悔したことがあります…。維持費、侮れませんよ。
相続した「遺産車売却」の方法と注意点
遺産の中に車が含まれていたけれど、「自分はもう車を持っているから不要だな」「ペーパードライバーだから運転しない」「維持費がかかるから手放したい」…そんな場合も少なくないでしょう。あるいは、車を相続したものの、それを元手に新しい車に買い替えたい、という方もいるかもしれませんね。
結論として、相続した車を売却することは、もちろん可能です。不要な車を現金化できれば、維持費の心配もなくなり、他のことにお金を使うこともできます。ここでは、相続した車を売却する際の具体的な方法と、知っておくべき注意点について解説します。
【最重要】売却前の名義変更は必須!
まず、絶対に忘れてはいけないのが、車を売却する前に、必ず相続人への名義変更(移転登録)を済ませておく必要があるということです。前のセクションでも触れましたが、亡くなった方の名義のままでは、法的にその車を売却することはできません。遺産分割協議(または100万円以下の場合の遺産分割協議成立申立書)に基づいて、いったん車を相続する方(あなた自身か、他の相続人)の名義に変更する手続きを、運輸支局で行う必要があります。この手続きを終えて、初めて売却が可能になります。
主な売却方法と比較
名義変更が終わったら、いよいよ売却です。主な売却先としては、以下のような選択肢があります。
- 中古車買取専門店:
- 特徴:ガリバー、ビッグモーター、アップル、ネクステージなど、全国に多くの専門店があります。車の買取を専門に行っているため、比較的高値での買取が期待できると言われています。
- メリット:複数の業者に査定を依頼することで、競争原理が働き、より高い査定額を引き出せる可能性があります。出張査定に対応している業者も多いです。
- デメリット:業者によって査定額に差が出ることがあります。複数の業者とのやり取りが必要になる場合も。
- ポイント:最近は、インターネットの一括査定サービスが便利です。一度、車の情報を入力するだけで、複数の買取業者からおおよその査定額の連絡がもらえます。ただし、多くの業者から電話がかかってくる可能性があるので、その点は留意しておきましょう。
- ディーラーへの下取り:
- 特徴:新しい車に買い替える際に、その購入先のディーラーに今乗っている車(相続した車)を引き取ってもらう方法です。
- メリット:車の購入から売却(下取り)までの手続きを、一つの窓口で済ませられるため、手間がかかりません。
- デメリット:一般的に、買取専門店の方が査定額(下取り額)は高くなる傾向があると言われています。
- 個人売買:
- 特徴:知人や友人、あるいはインターネットのオークションサイト(ヤフオクなど)やフリマアプリ(メルカリなど)を通じて、直接次の買い手を見つける方法です。
- メリット:業者の中間マージンがないため、うまくいけば最も高値で売れる可能性があります。
- デメリット:買い手探しから、価格交渉、名義変更手続き、代金の受け渡し、売却後のクレーム対応まで、すべて自分で行う必要があります。手間がかかる上に、金銭トラブルや手続き上のミスなどのリスクも伴います。初心者にはあまりおすすめできない方法かもしれません。
どの方法を選ぶにしても、慌てて一社だけで決めずに、複数の選択肢を比較検討し、愛車の適正な相場を把握することが、損をしないための重要なポイントです。
売却前の名義変更、ここを忘れる方が意外と多いんです。しっかりチェックしてから動きましょうね。
売却時の必要書類
売却する際には、一般的に以下の書類が必要になります。業者によって多少異なる場合があるので、契約前に必ず確認しましょう。
- 自動車検査証(車検証):原本が必要です。
- 自賠責保険証明書:有効期間中のもの。
- 印鑑登録証明書:発行後3ヶ月以内など、有効期限を確認。車の新しい所有者(あなた)のものです。
- 実印:譲渡証明書などへの捺印に必要。
- 自動車納税証明書(または納税確認の電子化に伴う証明):最新年度のもの。
- リサイクル券:預託済みであることを証明する書類。
- 譲渡証明書:旧所有者(あなた)の実印を押印。通常、業者が用紙を用意してくれます。
- 委任状:名義変更手続きを業者に代行してもらう場合に必要。実印を押印。これも業者が用意します。
- (場合により)相続を証明する書類:遺産分割協議書のコピーなどを求められることがあります。
売却益と税金について
最後に、税金の話です。車を売却して得た利益(=売却価格 - (取得費+売却費用))は、「譲渡所得」として所得税の課税対象になる可能性があります。
しかし、通常、私たちが通勤やレジャーなどに使う自家用車(非事業用)の場合、譲渡所得には年間50万円の特別控除があります。そのため、売却益が50万円以下であれば、所得税はかかりません。一般的な中古車の売却で、この50万円を超える利益が出るケースは稀ですので、ほとんどの場合、自家用車の売却で税金の心配をする必要はないと考えてよいでしょう。ただし、購入価格が非常に高かった車や、趣味性の高いクラシックカーなどが、購入時より高く売れた場合などは注意が必要です。不明な場合は、税務署や税理士に確認することをおすすめします。
使わない車を売却することは、維持費の節約になり、新たな資金を得る良い機会です。手続きを確実に進め、少しでも良い条件で売却できるよう、しっかり準備をしましょう。
遺産は共有財産?「親の遺産夫婦の共有財産」
遺産相続の話になると、特にご夫婦の間で「ちょっと気になるな…」と感じるのが、「相続で受け取った遺産って、夫婦の共有財産になるの?」という点ではないでしょうか。
例えば、夫であるあなたが親御さんから遺産を相続した場合、そのお金や財産は、奥様にも権利がある「夫婦のお金」として扱われるのか、それとも、あくまであなた個人のものなのか。あるいは、逆に奥様がご自身の親御さんから相続した遺産の場合はどうなのか。
この点は、お金の使い道や将来の財産分与(例えば、万が一離婚する場合など)にも関わってくるため、誤解がないように、基本的なルールを正しく理解しておくことがとても大切です。
結論から申し上げますと、相続や贈与によって取得した財産は、原則として、それを受け取った個人の「特有財産(とくゆうざいさん)」とみなされ、夫婦の共有財産にはなりません。
これは、民法という法律で、夫婦の財産が大きく二つに区別されているからです。
- 共有財産:これは、結婚している間に、夫婦が協力して築き上げた財産のことを指します。例えば、夫婦それぞれの給料から貯めた預貯金、一緒に住宅ローンを組んで買ったマイホーム、家族で使うために買った車などが典型例です。これらの財産は、夫婦の協力によって得られたものと考えられるため、離婚する際には財産分与の対象となり、原則として夫婦で半分ずつに分けることになります。
- 特有財産:これは、結婚する前から各自が持っていた財産や、結婚した後であっても、夫婦の協力とは関係なく、個人的に取得した財産を指します。そして、この「個人的に取得した財産」の代表例が、相続によって受け継いだ遺産や、贈与によってもらった財産なのです。これらは、夫婦の努力で築いたものではなく、個人の家系などから引き継いだものと考えられるため、原則として離婚時の財産分与の対象にはなりません。
ですから、あなたが親御さんから相続した遺産(現金であれ、不動産であれ、あるいは車であれ)は、法律上はあなた個人の「特有財産」ということになります。同様に、もし奥様がご自身の親御さんから遺産を相続した場合も、それは奥様の特有財産です。
この原則を理解しておくと、例えば「相続した遺産で車を買う」場合にも応用できます。あなたが相続した遺産(特有財産)を使って車を購入した場合、その車も基本的にはあなたの特有財産から形を変えたもの、と考えられるわけです(もちろん、実質的に夫婦共有の車として使うことは全く問題ありません)。
ただし、注意点もあります。
特有財産であっても、例えば相続した預金を夫婦の共有口座に入れて生活費として使ってしまい、どちらのお金か区別がつかなくなってしまった場合や、相続した不動産の維持管理(リフォーム費用など)を夫婦の共有財産から支出していた場合など、夫婦の協力によってその価値が維持されたり、増加したりしたと認められる場合には、例外的に財産分与の際に考慮される(一部が共有財産とみなされる)可能性もゼロではありません。
法律上の扱いはさておき、最も大切なのは夫婦間のコミュニケーションです。遺産という大きなお金が絡む問題は、時に夫婦関係に影響を与えることもあります。特有財産だからといって、配偶者に何も相談せずに使い道を決めてしまったり、隠し事をしたりすると、不信感や将来のトラブルの原因になりかねません。「こういう遺産が入ったんだけど、どう使うのが良いと思う?」「車の買い替えに使いたいんだけど、どうかな?」など、オープンに話し合い、お互いの気持ちや考えを尊重しながら、一緒に使い方を考えていく姿勢が、円満な夫婦関係を維持するためには不可欠と言えるでしょう。
Q&A:遺産と車のよくある質問
ここまで、遺産で車を購入・相続する際の手続き、税金、選び方などについて詳しく見てきましたが、もしかしたら「これはどうなんだろう?」という細かい疑問がまだ残っているかもしれませんね。
そこで、このセクションでは、遺産と車に関してよく寄せられる質問とその回答を、Q&A形式でいくつかご紹介します。あなたの疑問解消のヒントになれば幸いです。
Q1. 車の相続手続き(名義変更など)は、自分でできますか? 難しいですか?
A1. はい、ご自身で行うことも可能です。必要な書類(戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書、車庫証明書など)を揃えて、新しい所有者の住所地を管轄する運輸支局(普通車の場合)または軽自動車検査協会(軽自動車の場合)の窓口で手続きを行います。
ただし、平日の昼間しか開庁していない、必要書類が多くて集めるのが大変、書類の書き方がよく分からない、といった理由で、難しいと感じる方も少なくありません。
もし手続きに不安がある場合や、時間がない場合は、行政書士に依頼するのが一般的です。行政書士は書類作成と申請代行の専門家ですので、スムーズに手続きを進めてくれます。依頼費用は、一般的に2万円~5万円程度が相場ですが、ケースによって異なりますので、事前に見積もりを取るとよいでしょう。また、車の購入と同時に手続きを行う場合は、ディーラーや中古車販売店が代行してくれることもあります(別途手数料がかかる場合が多いです)。
Q2. 相続税の申告が必要になった場合、いつまでに何をすればいいですか?
A2. 遺産の総額が基礎控除額を超え、相続税の申告が必要になった場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出し、納税を済ませる必要があります。車の評価額を含め、すべての遺産を正確に評価し、申告書を作成するのは専門的な知識が必要です。期限内に適切な申告・納税ができないと、延滞税などのペナルティが課される可能性もありますので、早めに税理士に相談することを強くおすすめします。
Q3. 故人が自動車税を滞納していた場合はどうなりますか?
A3. 自動車税の納税義務も、相続の対象となります。したがって、もし故人が自動車税を滞納していた場合、相続人がその滞納分を引き継いで支払う必要があります。名義変更手続きの際に、納税証明書の提示を求められる場合もありますので、滞納がある場合は速やかに解消しておきましょう。
Q4. 複数の相続人で車を共有名義にすることはできますか?
A4. はい、法律上は可能です。遺産分割協議書に、複数の相続人の共有名義で相続することを明記すれば、そのように登録できます。ただし、車を共有名義にすると、将来的に売却や廃車をする際に共有者全員の同意と書類が必要になったり、自動車税や保険料の負担者を誰にするかなど、後々手続きが煩雑になったり、もめ事の原因になったりする可能性があります。特別な理由がない限り、特定の相続人が単独で相続する方が、後々の管理はしやすいと言えるでしょう。
Q5. 遺産分割協議がなかなかまとまりません。車を早く使いたいのですが…
A5. 遺産分割協議が成立するまでは、車は相続人全員の共有状態ですので、原則として特定の相続人が自由に使用することはできません(ただし、相続人全員の合意があれば別です)。もし協議が長引きそうな場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることを検討しましょう。調停委員が間に入り、話し合いを進めてくれます。それでもまとまらなければ、審判手続きに移行し、裁判官が分割方法を決定します。いずれにしても、法的な手続きが必要になる場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
これらのQ&Aで、少しでもあなたの疑問が解消されたでしょうか? 個別の状況によって対応が異なる場合もありますので、迷ったときは専門家への相談も考えてみてくださいね。
まとめ:遺産を活かしたカーライフのために

さて、ここまで「遺産で車を買う」というテーマについて、様々な角度から詳しく解説してきました。いかがでしたでしょうか?
大切なご家族が残してくれた遺産。それを活用して、新しい車と共に新たなカーライフをスタートさせることは、きっとあなたの毎日をより豊かで便利なものにしてくれるはずです。故人への感謝の気持ちを形にする、素敵な方法の一つかもしれませんね。
この記事でお伝えした情報が、あなたが抱える疑問や不安を少しでも解消し、自信を持って次のステップに進むための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。
もちろん、手続きや税金のことで分からないこと、不安なことがあれば、決して一人で抱え込まず、行政書士、税理士、弁護士といった専門家の力を借りることも考えてみてください。的確なアドバイスが、あなたの悩みを解決してくれるはずです。
あなたの新しいカーライフが、素晴らしいものになることを心から願っています!
まとめ
- 車は相続財産となり名義変更が必須
- 車検証で所有者とローン有無を確認
- 相続手続きには原則「遺産分割協議書」が必要
- 100万円以下の車は簡易手続きが可能
- 簡易手続きには公的な査定証が必要
- 車も相続税の対象、基礎控除超過に注意
- 相続税の車評価は購入価格でなく「時価」
- 親からの購入支援は110万円超で贈与税対象
- 車選びは維持費含めた総予算と生活設計で
- 相続遺産は夫婦共有でなく「特有財産」
- 不要な相続車は名義変更後に売却可能
- 不明点は行政書士や税理士等へ相談を